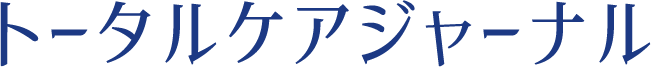社会福祉法人のM&Aとは?
一般的なM&Aにおいては、“売り手となる企業”が運営する会社や事業を、“買い手となる企業”が株式の形を用いて買い取る仕組みとなっています。
一方、社会福祉法人がM&Aを実施する場合、社会福祉事業や公益事業、収益事業を目的に設立された法人であるため、株式の発行がありません。
| 社会福祉事業 | 【一種】 ・児童養護施設 ・特別養護老人ホーム ・障害者支援施設 ・救護施設 など 【二種】 ・保育所 ・デイサービス ・ショートステイ ・訪問介護 など |
| 公益事業 | ・子育て支援事業 ・人材育成事業 ・入浴、排せつ、食事等の支援事業 ・老人保健施設、有料老人ホーム、介護予防事業の経営 ・行政や事業者等の連絡調整事業 |
| 収益事業 | ・駐車場 ・貸ビル ・公共施設内の売店 |
社会福祉法人におけるM&Aでは、株式による対価ではなく、合併もしくは事業譲渡の手法を用いて買い手となる企業に営業権が移ることになります。
社会福祉法人のM&Aに関する国のガイドライン
社会福祉法人がその役割(公益事業である社会福祉事業)を全うできるように、合併や事業譲渡等の手続きや留意点についてまとめた「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」が厚生労働省によって策定されています。
また、社会福祉法人が合併・事業譲渡等を実施する場合のポイントなどが詳しく記載されている「合併・事業譲渡等マニュアル」も厚生労働省が周知しています。
社会福祉法人のM&Aは、上記で紹介したガイドラインとマニュアルに沿って実施されます。
社会福祉法人のM&Aで用いる2種類のスキーム
株式を発行しない社会福祉法人のM&Aで用いられるスキームは、「合併」と「事業譲渡」の2種類となります。
スキーム1:合併
社会福祉法人の合併は、合併先も社会福祉法人に限られるものとなっています。なお、合併には以下の2種類があります。
吸収合併
一方の会社の法人格のみを残し、他方の会社の法人格を消滅させ、消滅する会社のすべての権利義務を、合併後も存続する会社に承継させる方法。
新設合併
全ての法人格が消滅し、新たに設立する新法人へすべての権利義務を承継させる方法。
法人の合併には、以下のような効果が期待できます。
- ・経営基盤を強化し、事業の安定性・継続性を高める
- ・ほかの法人の経営資源や人材、ノウハウなどが集約され、事業効率化やサービスの品質向上が実現する
- ・法人間での人事交流が促進され、職員のスキルが向上したり組織が活性化したりする
なお、社会福祉法人の合併は、合併先も社会福祉法人に限られるものとなっています。
スキーム2:事業譲渡
事業譲渡とは、特定の事業を継続するために、該当する事業財産を他の法人に譲渡する手法です。
事業譲渡には、以下のような効果が期待できます。
- ・継続が難しい事業の継続
- ・経営資源や人材の譲渡による即戦力の獲得と事業展開・拡充の負担軽減
そのほか、経営基盤の強化やサービスの品質向上など、合併と同じような効果を得られます。
なお、事業を営む建物や土地だけでなく、事業に必要な有形および無形の財産をすべて譲渡することになります。
ただし社会福祉法人の事業譲渡は、一部の事業のみ可能(譲受先法人が社会福祉法人でない場合、第一種福祉事業は譲渡不可)となっており、社会福祉事業のすべてを譲渡することはできません。
社会福祉法人がM&Aを利用する背景
社会福祉法人はM&Aを利用する事で得られる事業効率化の効果を元に、今まで取り組むことが難しかった福祉サービスの充実を図ったり地域住民のニーズに合わせた新しいサービス提供を目的としています。
また、M&Aを通じて地域住民とのつながりを深めることも期待されることからも、少子高齢化に伴うニーズに対して柔軟な対応を求められています。
少子高齢化による地域社会のニーズの変化
少子高齢化により、社会福祉事業に求められる地域社会のニーズが多様化・複雑化しています。
ニーズの変化に対応できるよう“法人の新陳代謝の活性化”を目的の一つとしたM&Aを実施するところも多く、合併や事業譲渡によりサービス向上を目指します。
経営状況を改善・事業を再生したい
社会福祉法人では零細企業も多く、経営状況が悪化しているケースも多く見られます。経営状況が悪くなっている企業が、改善や事業再生に向けてM&Aを活用することがあります。
M&Aによって経営状況の良くない事業でも残すことができ、利用者へのマイナスとなる影響を最小限に抑える効果が見込めるためです。
社会福祉法人がM&Aを活用するメリット
社会福祉法人がM&Aを活用することで、サービスの質向上・新しい事業の拡大・事業効率化・人材やノウハウの獲得といったさまざまなメリットをもたらします。
その中でも、サービスの提供品質に対して利用者側も強い関心を持っています。当然ながら、ニーズを満たすためには品質の高さは”サービス業”である介護業にも強く求められています。
また、こういった品質面の高さを維持することは地域で長期間事業継続できる要素にもなります。
高い質のサービス提供
経営状況が悪化している社会福祉法人では、提供可能なサービスが限定されていたり、地域社会が求めるニーズに応えられるだけの経営基盤を持っていなかったりする場合も見受けられます。
M&Aを用いることによって、提携先の社会福祉法人の人材やノウハウ、設備を活用することでこれらのネガティブ要素を払拭し、サービスの質の向上につなげられます。
また、両方人が保有しているそれぞれのスキル・知識・経験を共有することによって、人材育成にも役立ちます。
効率的な事業展開
M&Aを用いた合併・事業譲渡を行うことによって、相手先の社会福祉法人が有する人材・ノウハウ・設備を獲得することにつながるため、スケールメリットを得ることが可能です。
それにより、新たなサービス開発や資材調達のコストを削減し、効率的に事業展開・拡大ができます。場合によっては、施設の確保や増設なしで新事業を展開できることもあり、経営の再建に役立つこともあります。
経営基盤の強化
法人同士の合併や事業譲渡によって経営基盤の強化が期待できます。それにより、法人としての運営体力を高めることにつながります。
ひいては社会福祉法人の主目的である公益性の高い事業の安定性を向上させ、継続が難しいケースにおいては事業再建と継続に寄与することも可能です。
社会福祉法人が合併する際の流れ

経営基盤の強化や事業展開の効率化など、さまざまなメリットがあるM&Aですが、どのように手続きを進めたら良いのでしょうか。ここでは、社会福祉法人が合併する際の流れを紹介します。
1.合意形成
社会福祉法人が合併するにあたり、まずは合併相手の法人と合意形成を行います。合意形成のフローは以下のとおりです。
- 秘密保持契約を締結する
- 合併する法人間で事前協議を行う
- 基本合意書の作成・締結を行う
合併する際には、お互いに自社の内部情報を開示することになるため、まずは秘密保持契約を結びます。契約の締結については、各法人の理事会などで承認・報告を行うのが一般的です。
続いて、お互いの認識を合わせるために、合併する目的や合併後の事業内容などについて協議を行います。このとき、役員選任や職員の処遇などについても決めておきましょう。
そして、合併の重要事項について記載した基本合意書を作成・締結し、内容に対して両者合意していることを示します。
2.役員等の検討
合意形成が完了したら、次は合併後の法人の評議員・理事・監事について検討します。
評議員や役員については、資格や権限などが明確に定められているため、条件に合った人材を選びます。また、定員数が変わる場合は、定款の変更が必要です。
なお、以下のいずれかに該当する場合は会計監査人を設置する義務があるため、会計監査人についても検討しなければなりません。
- ・合併後の決算で事業活動計算書におけるサービス活動収益が30億円超
- ・貸借対照表の負債が60億円超
3.合併契約書の作成
社会福祉法人の合併において、合併契約の締結は必須です。契約内容について協議して合併契約書を作成し、各法人の理事会などで承認を行います。このときの決議について、議事録を残すことも大切です。
また、契約締結にあたり、社会福祉法人を吸収合併する側とされる側の以下の項目を定めておく必要があります。
- ・吸収合併する側の法人名と所在地
- ・吸収合併される側の法人名と所在地
- ・合併の登記予定日
- ・合併後の職員の処遇について
合併契約書の内容に双方が合意したら、評議員会の決議を経て合意契約を締結します。社会福祉法人の合併契約の締結には、評議員会の決議・承認と議事録の作成が必要なので、忘れないようにしましょう。
4.事前開示および閲覧の請求
社会福祉法人の合併を行うにあたって、双方の契約内容を事前開示する必要があります。
また、内容についての閲覧請求に備えるために、情報を記録した書類または電磁的記録を重たる事業所に置いておかなくてはなりません。なお、吸収合併する側とされる側で開示期間が異なるため注意しましょう。
- ・吸収合併する側:契約の決議を行う評議員会が開催される2週間前から合併の登記日までの期間
- ・吸収合併される側:契約の決議を行う評議員会が開催される2週間前から合併の登記後6ヶ月経過するまでの期間
5.評議員会の承認
社会福祉法人の合併では、両者の評議員会で合併契約の承認を得ることが求められます。
その際、被合併法人の負債が、合併法人の資産額を超過する場合は、その点についても説明します。評議員会の決議内容については、しっかりと議事録に残してしておきましょう。
6.所轄庁の認可
社会福祉法人の合併では、評議員会だけでなく所轄庁に申請し、認可を受けなければなりません。合併認可申請書・合併理由書などさまざまな書類が必要なので、所轄庁の担当窓口で確認しましょう。
7.債権者保護手続き
上記に加えて双方における債権者保護手続きも必須です。主な手続きとしては、以下のようなものがあります。
- ・債権者への催告で必要となる貸借対照表の要旨の作成
- ・合併に異議申し立てをする機会を設けるための公告の実施
- ・金融機関などの個別の債権者への催告書の送付
- ・債権者が異議を述べた場合の対応
8.登記手続き
合併契約が締結されたら、合併法人、被合併法人共に登記手続きを行います。
- ・吸収合併する側:変更登記を行う
- ・吸収合併される側:解散登記を行う
登記申請を行う場所は、事業所所在地を管轄する法務局です。
9.事後開示
登記手続きが完了したら、合併側の社会福祉法人は速やかに事後開示事項を記載した書類、または電磁的記録を事務所に置きます。ここで開示しなければならない内容は以下のとおりです。
- ・登記日
- ・債権者保護手続きの状況について
- ・合併した法人から承継した権利や義務について
- ・事前開示で記載していた内容について
そのほか、今回の合併に関わる重要な内容があれば、それについても記載しておきます。また、閲覧請求があったときにすぐに対応できるよう、準備しておきましょう。
社会福祉法人が事業譲渡する際の流れ

続いて、社会福祉法人が事業譲渡する際の流れについて解説します。
1.事前調査
社会福祉法人の事業には、許認可が必要なものが多くあります。まずは、そもそも事業譲渡ができるのかどうかを、関係省庁に確認するなどして調査しましょう。
あわせて、譲渡先の法人が譲渡された事業を継続していけるかどうかも確認する必要があります。社会福祉法人の事業譲渡においては、利用者がサービスを利用し続けられるかが重視されるため、事業が続けられない場合は譲渡することができません。
譲渡可能であることが確認できたら、合併の場合と同じく以下の手続きを進めましょう。
- ・内部情報共有にあたり、秘密保持契約を締結する
- ・譲渡契約について事前協議を行い、認識をすり合わせる
- ・契約内容を確認し、基本合意書を作成・締結する
また、これらの工程を円滑に進めるために、譲渡する側・される側それぞれに委員会などを設置し、担当者を決めておきましょう。
2.事業譲渡契約
事業譲渡の条件や内容などが確定したら、事業譲渡契約書を作成して契約を締結します。事業譲渡契約書の作成は、法的に義務付けられているものではありません。
しかし、契約内容を書面に残しておくことで、認識の違いなどによるトラブルを防止できるため、きちんと作成しておくのがおすすめです。
また、双方の理事会などで決議・承認を得て、議事録に残すことが望ましいとされています。
3.事業にかかる各種申請
事業譲渡するにあたり、事業を譲渡する側の社会福祉法人は、以下のような申請手続きを行う必要があります。
- ・基本財産の処分申請:譲渡する事業の基本財産を処分するための申請手続き
- ・補助金にかかる財産処分の申請:国や都道府県から補助金を受け取っている事業の財産を処分するための申請手続き
また、下記の申請については、両社が行わなければなりません。
- ・施設の廃止申請および設置申請:譲渡する側の法人は施設を廃止するため、譲渡される側の法人は施設を設置するための申請手続き
- ・付随機能の申請:譲渡事業に保育所や診療所が付属するなど、別途何らかの機能が付属する場合の申請手続き
4.定款の変更
事業譲渡では、譲渡側、被譲渡側共に定款の変更が求められます。
定款変更は譲渡する側は事業の廃止・基本財産の処分について、譲渡される側は事業の追加・基本財産の増加について評議会で決議し、関係省庁にて申請手続きを行うことで完了します。
5.資産や負債などの移転手続き
事業譲渡では、基本財産のほかに負債や不動産などを譲渡することもあります。この場合、これらを移転する手続きが発生します。
事業譲渡契約とは別に、基本財産・負債の譲渡や不動産の登記移転に関する契約を締結しましょう。
社会福祉法人のM&Aにおける注意点
社会福祉法人のM&Aにおける注意点として最も意識すべき点としては対価設定に対する取り扱いです。
公益性・非営利性を求められる社会福祉法人は事業の適切な評価とともに法人外への対価性のない支出が認められていないことからも大きな規制がかかる事を理解してM&Aを進める必要があります。
対価設定について
社会福祉法人は株式を発行していないため、“持分”という概念がありません。さらに、公益法人である以上、社会福祉法人以外に向けた対価性のない支出は禁止されています。合併においては、吸収される法人に対価が支払われることはありません。
事業譲渡の場合、譲渡する事業の見積価値以上の対価設定が必要です。そうでない場合、法人外への資金流出に該当すると考えられます。
財産などの対価を設定する場合には、財務調査などによって適切な事業価値の見極めが必要となります。
許認可に関する手続きについて
財産や定款に関する手続きには所轄庁の許認可が必要となります。合併や事業譲渡をする前や決定した際には、行政機関と連携して進めていくことが重要です。
譲渡側の職員や利用者への説明について
合併や事業譲渡を行う場合、利用者やその家族には、事前にしっかりと説明しなければなりません。事業譲渡の場合、利用者との再契約が必要になるケースもあります。
また、譲渡される側の職員に対して、雇用条件の変更が発生する場合、同意書などを交わす必要があります。
まとめ
社会福祉法人のM&Aを検討している場合、専門家によるコンサルティングを受ければ、第三者的な観点から有益なアドバイスを得られます。介護業界は他の産業と異なる特性があるため、介護業界のことをよく知る専門家に相談するのがベストです。
土屋総研は、日本全国で福祉に携わる株式会社土屋グループの総合研究部門です。福祉サービスを利用する方の地域生活を維持することを目的として、共に地域を支える同業者へのコンサルティングも比較的安価で行っています。
事業の買収、譲渡(M&A)についてもノウハウがありますので、ぜひご相談ください。
【 土屋総研へのお問い合わせはこちら 】