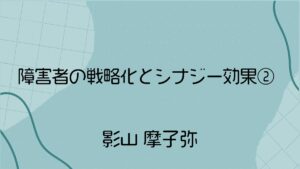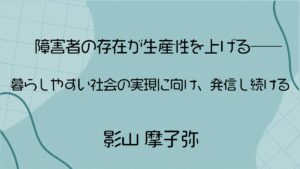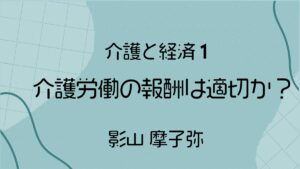株式会社土屋は、重度訪問介護サービスを提供することで、障害をもった多くの人達の暮らしを支えています。土屋で顧問を務めている安積遊歩。障害があるということで幼いころから理不尽を強いられてきた彼女は、当事者であることを原動力に社会に向けてメッセージを発信し続けています。そんな安積の生き方と想いに迫ります。
互いに尊重し合える社会で生きたい――普遍的な平和を求めて――

安積は、骨が弱いという先天的な特徴を持っています。身長は109センチ、体重27キロ。20歳までに骨折を20回以上経験しました。
安積 「障害があることで、大人社会から理不尽な扱いを受けてきました。生後40日目から1日おきに男性ホルモンを注射されたり、生体実験のような治療をされたりもしました。このような経験もあって、小さいころから、もっと平和な社会があればいいのにと感じていました」
互いが尊重しあい助け合える、平和な社会で生きたい――。そんな想いを胸に大人になっていった安積は、平和からはあまりにも遠い社会の現実を心身に突きつけられます。
安積 「戦争、競争、経済の活性化。そんなものばかりでこの世界は回っています。成長するにつれ、世の中の現実を知って失望が深くなっていた頃に、日本国内の障害者運動に出会い、アメリカでは日本よりずっと多様性が受け入れられているのだということも知りました。ぜひ実際に見てみたいと思い、海外派遣事業を活用して、車椅子でアメリカのバークレーに渡ったのです」
この渡米は、1983年、安積が27歳のときの挑戦でした。現地に入り、安積は自立生活センターで障害者支援の研修を受けます。この研修の中で、特に印象に残ったのは「ピアカウンセリング」というカウンセリング手法でした。
安積 「『ピア』とは『仲間』を意味する言葉で、障害をもつ者同士、女性同士など、同じ背景を持つ人同士で、対等な立場で互いの気持ちを聞き合います。私自身、話をしていく中で『本音で生きていいんだ』と思えて、ハッとさせられたことを今でも強く覚えています」
この経験を活かし、日本に帰国後、ピアカウンセリングの第一人者として活躍するようになった安積。アメリカに滞在したのは半年という短い期間でしたが、日本では考えられないような光景をたくさん目にすることができました。
安積 「多様性を尊重しようとする社会が当時のアメリカにはありました。もちろん、エイズの人たちへの差別も顕在化してきていましたが、私の研修先があったバークレーでは当時人口の半分がLGBTの人ではないかと言われていました。
また、ある日郵便局に並んでいたら、日本では考えられないようなバラエティ豊かな人々が列をなしていることに気が付いたのです。肌の色も、言葉も、年齢もバラバラ。車椅子の人も、盲導犬をつれた人もいました。誰が“普通の人”なのかなんてさっぱりわからないその光景は、人を排除せず、尊重し合う社会の姿そのものでした」
重度訪問介護の必要性と認知を広めることで、暮らしやすい社会を作る

アメリカでの若き日の感動を胸に、日本社会の改善を目指して、安積は長年、障害を持つ当事者としての活動を続けてきました。現在は、株式会社土屋で顧問も務めています。その背景には、土屋のCEOである高浜との交流がありました。
かつて高浜は、株式会社土屋を創業する前に、安積が登壇していたシンポジウムで彼女の話を傍聴したことがありました。そこで安積の話に感銘を受け、直接会いに行ったことから2人の交流がスタート。その後、高浜は重度訪問介護の事業を行うべく、土屋を立ち上げ、安積はその想いに深く共鳴し、土屋に顧問として関わることになったのです。
土屋の主軸の事業である重度訪問介護は、重い障害をもつ人にとって重要な制度。必要に応じて、24時間などの長時間の見守りをオーダーすることができるため、当事者主導の制度ともいわれています。重度訪問介護こそ、社会をより良くしていくために不可欠なものだと、安積はかねてより考えていました。
安積 「土屋の顧問になる前から、重度訪問介護というシステムのすばらしさを発信してきました。私がリーダーシップをとっていたCILの従業者養成研修の講座では、最初の頃は私一人で何項目も担当していました。始まった当時は車椅子でエスカレーターに乗る方法を教えたりもしていましたが、CILの事務局から、危険だからそれは課程のなかで教えないでください、と言われたりね。でも当事者としてわかることはできる限り伝えたかったりしてね」
時代が変わるにつれて、世の中の少しずつ穏やかになった側面を感じているものの、安積は、いつも厳しい目線で社会を見ています。障害があっても暮らしやすい社会のために、これからも重度訪問介護の仕組みや必要性を訴えていきたいと語ります。
安積 「現在は、重度訪問介護を目指す人たちに向けてスピーチをしたり、Webサイトでコラムを執筆したりしています。そもそも、重度訪問介護という仕事があることを知らない人もいると思うので、特に若い人たちに向けてその存在を伝えているのです。こうして伝えることは、土屋の顧問としての何か特別な仕事というよりは、重度訪問介護というシステムをより多くの人に知ってもらうための、以前からの活動の一環なんです」
互いを隔離する現代社会。存在への優しい眼差しが不信へと変わっていく

安積には娘がいます。彼女も安積と同じように、先天的に骨が弱い性質を持って生まれました。
安積 「私と同じ特徴を持った娘ですが、自分とは真逆の育て方をしました。医者にはほとんど連れていきませんでしたし、骨折してもギプスも手術もさせませんでした。そうやって成長した結果、人間的な深い穏やかさを持った子に育ってくれました。娘は今、ニュージーランドで暮らしています」
20〜30年前くらいからニュージーランドでは、行政主導の障害をもつ人を隔離分離せず脱施設化政策をすすめてきました。行政が主導する障害をもつ者を隔離・分離せず脱施設化をしていこうという動きがあるといいます。
安積 「『障害のない人たちが障害をもつ人を施設に隔離し排除することはよくない』と気づいて、それが制度にも反映されている。しかしそれはまた『してもらう』『作られる』という、関係性の踏襲にもある意味なっているわけです。
日本の『青い芝の会』をはじめとする当事者運動は、自ら声をあげ状況を開拓してきました。そういった運動や議論なんかを通して『障害とは何か』『生きるということはどういうことか』ということを、個々人がそれぞれに深めてきました。
『“私は・私たちは”こういうものや制度が必要だ』と、障害をもつ者側からの発信をきちんと行ってきたニュージーランドは、もちろんバリアフリーや差別解消は進んでいますが、私には当事者側からの提言によるベクトルとはあまり見えません。寄り添ってくれてはいるんだろうけど根本的には措置と似通ってきてしまっているのではないか。障害のない人が『障害をもつ人はこうすればいい』というフレームを囲ってしまうという点において。
娘も、『当事者として声をあげる必要がやっぱりあるな』と感じているようです。『自分が違う・フィットしないと思うことに対して何も言わないということはやっぱり変でしょう』と」
日本社会で起きた行政主導の取り決めについて、安積には忘れがたい苦い記憶があります。1979年、養護学校の義務化が法律によって決められました。障害をもつ子が養護学校へ通うことが義務付けられ、一般の小学校・中学校に通うことが制限され、地域によっては完全に排除されています。
安積 「障害のある子ない子を分離隔離する法律に、ものすごく腹が立ちました。後に交通バリアフリー法や優生保護法の改訂などに繋がっていくような運動は当時からあって、一定の改革が続いてきていたのに、非常に悲しいことでした。
隔離して教育をすると、子どもたちは障害をもつ人と出会うことなく大人になります。同じ街で暮らしていても、お互いがエイリアンのように見えて近づきにくくなってしまうんですよね。結果、2016年のやまゆり園事件のような事態へと繋がっていくわけです」
こんな社会になってはダメだ――養護学校義務化に関する悔しさは、今でも安積の胸に強く残っています。
安積 「たった一回きりの人生、穏やかに、幸せに生きたいじゃないですか。現状障害のない人でも、事故や災害、食品汚染や環境汚染などによって、ある日突然、障害や病気をもつ当事者になることになる可能性は十分にあります。そうなったとき、突然隔離され、優生思想によって『いない方が良かった』みたいなことをいわれたらどうでしょうか」
誰しも、身体の変化は起こりうる。だからこそ、自由に生きられることを保障してくれる社会を目指したい。そうしない限り、真の意味での平和はないと安積は考えています。
「争えない身体」を持っている人こそ、強い。深い穏やかさで平和の礎を築く

さらに安積は、現代の男社会の構造を嘆かわしく思っていると話します。
安積 「男性は、言うなれば『争える身体』を持っています。争える身体を持った人は、男性優位的な競争社会に組み込まれ、争いに参加することを強制され、参加しなければ軽蔑さえされてしまう。その結果として、争える身体を持った人が次第に穏やかさを失っていき、平和が遠ざかっていくのです。
しかし、このようなことを話しても、さっぱり通じないことが多いですよ。競争原理の中で生きることに慣れきっているからなかなかすぐにピンとこない人が多いのでしょう」
男社会で必死に生きる「争える身体」の持ち主たち。彼らからすれば、「争えない身体=弱い・ダメな身体」という認識なのだろうと安積は憂います。
しかし、無意識にも加害者である彼らの苦悩は、実は被害者の苦しみよりも深く、今の社会では到底受け止めることができないのではと安積は考えます。
安積 「だからこそ、重度訪問介護が必要なのです。障害をもたない人たちは、自分が特権階級・加害者として生きている自覚がない。一方、争えない身体を持つ私たち障害者は、深い穏やかさを知っています。男社会で暴走するしかない男性たちを止めて、平和のための礎を築くことができるんです。争えない身体を持っている人こそ、その穏やかさゆえに、本当の意味で強いといえるのではないか。これを声を大にして世界中に伝えていきたいですね」
最後に、土屋で重度訪問介護の仕事をしているスタッフに向けて、安積から激励の言葉をおくります。
安積 「重度訪問介護で障害をもつ人に向き合うということは、彼ら/彼女らの抱えるすべての問題を自分ごととして感じる、ということを意味します。障害をもつ人の心に寄り添うことで、相手の気持ちを考える想像力を、本当の意味で鍛えることができるでしょう。自分自身の想像力の豊かさに期待して、ぜひ頑張ってください。
また、たとえその後、自分自身のはたらく先が変わったとしても、重度訪問介護で関わった障害をもつ人との時間は、きっと人生を変える財産になりますから、ぜひじっくりと関係性を作ってほしいです」
穏やかに暮らせる社会を目指して発信を続ける安積。そのまっすぐな想いが、これからの社会が進んでいくべき道を、そっと照らしています。