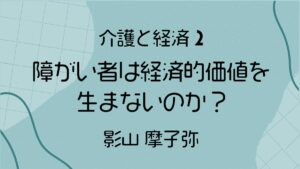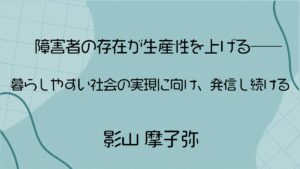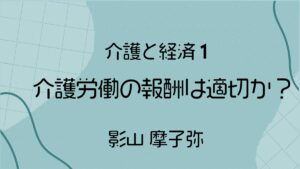医学部在学中、ラグビーの試合中の事故で脊髄を損傷した雪下 岳彦。車椅子生活になってから医師免許を取得し、アメリカ留学にもチャレンジ。現在は母校の大学で非常勤講師を勤め、千葉ロッテマリーンズのチームドクターとしても活躍しています。医師でもあり障害者でもある雪下ができること、目指すものを語ります。
障害を持ち「肉体的サポートだけでなく、精神的なサポートが必要」と痛感

25年前の夏。順天堂大学医学部在学中の雪下は、ラグビー部生活6年間の集大成、最後の夏の大会に出場していました。しかし、試合中に頭から地面に落ち、言い渡された診断結果は「脊髄損傷」。「その日から、第2の人生が始まったといっても過言ではない」と雪下は語ります。
雪下 「怪我をするまでは精神科への興味はありませんでした。しかし、自分がこうして大きな怪我をしたことで、肉体的な辛さだけでなく、回復するまでの精神的なストレスの大きさも痛感したのです」
リハビリ生活の中で医師免許を取得し、順天堂医院精神科にて研修修了。その後はハワイ大学(心理学)、サンディエゴ州立大学大学院(スポーツ心理学)に留学をしました。そして2011年、順天堂大学大学院医学研究科にて自律神経の研究を行い、医学博士号を取得したのです。
雪下 「スポーツ系のサポートは、肉体的な部分に着目されがちですが、実際は精神面でのサポートも必要。自分の経験を通じて、精神的な部分や、自律神経のバランスなどをサポートをしていこうと心がけています」
こうした経歴からもうかがえるとおり、雪下は大学在学中の事故後も変わらず学びを深めていき、現在は順天堂大学の医学部とスポーツ健康科学部の非常勤講師を兼任。また、2020年より千葉ロッテマリーンズのチームドクターにも就任し、メディカルサポートを通じて選手の健康管理をするなど、その活躍はとどまる所を知りません。
現場に足繁く通うことは難しいものの、データのやり取りはメールでも可能。障害の有無は、あまり関係なかったといいます。
雪下 「私の仕事は『メディカルサポートをしている人たちのサポート』。直接選手をサポートしているチームドクターやトレーナーからの質問に分かりやすく答えたり、血液検査の結果から『より強くするのはどうしたらいいか』というアドバイスをしたりしています」
スポーツをしたくてもできない障害者は大勢いるーー見えない感覚の差
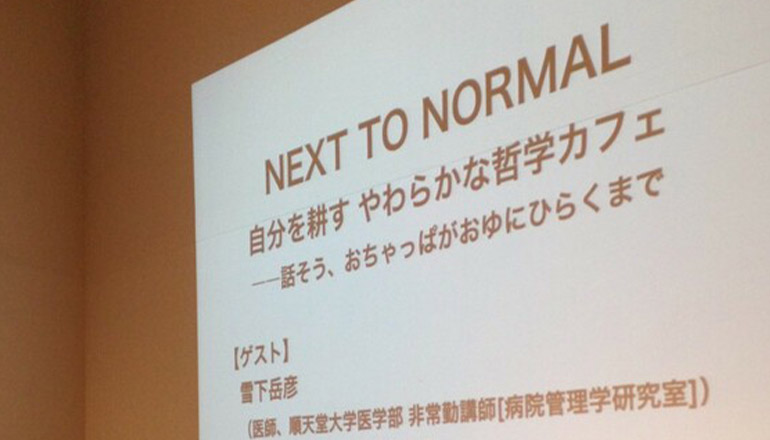
多方面で講演を行ってきた雪下。2016年から2年間、スポーツ庁にも参与しました。障害当事者でありつつ、スポーツのメディカルサポートにも携わっている雪下に求められたのは、その両方の立場を活かしたアドバイス。障害者のスポーツ参加や観戦に関する課題に取り組みました。
雪下 「障害者スポーツ振興室で働いている人達が、最初から障害に関して詳しい知識を持っているわけではありません。スタジアムのトイレ問題や、アクセスについてなど、健常者にもなるべく分かりやすいように、当事者として課題を伝えました」
2021年には東京パラリンピックもあり、障害者スポーツに関する認知も高まってきたものの、社会ではまだまだ誤解されている部分が多いといいます。
雪下 「障害者スポーツができる人は、障害者の中でも比較的状態が良い人。スポーツがしたくてもできない人も大勢いるんです」
スポーツ経験がある雪下。だからといって障害者スポーツができるというわけではありません。しかし、「車いす」=「車いすバスケやってるの?」と聞かれることも多いそう。
雪下 「障害を持った人の中には、“どうせできない”と諦めてしまっている人もいれば、そもそもスポーツに対しての興味が薄い人だっています。全員がパラリピアンのような人達ではありませんからね」
健常者と障害者の間には、このような見えない感覚の差が結構あると雪下は感じています。
雪下 「障害者が『スポーツをする』ということは、スポーツをする場所まで一人で行けるのか、付き添いがいるのかも考える必要がありますよね。たとえ競技場がバリアフリーであったとしても、そこに着くまでのアクセスだって重要。電車やバスの使いやすさを含め、家から競技場まで全てを考えなければいけないのです。この部分までを理解してもらう難しさを、スポーツ庁時代には感じました」
健常者・障害者の視点、医師としての知識を持ち、スポーツ経験者の雪下だからこそ、異なる立場の人の架け橋になり得るのでしょう。
雪下 「事実を伝えたからといって、急に変えることは難しいものです。ただ、相手のことを想像するという視点を持つのと持たないのでは、アプローチが変わってくるはず。私が気づいたことを、根気強く何度も伝え続けました」
誰しも、みな同じ人間。サポートする側の人をケアし、世の中のQOLを上げたい

雪下と土屋の出会いは、現在、土屋パブリッシングの編集長として活躍している大山 景子がきっかけだったといいます。大山は、編集者として出版社に勤務していた2012年春、大きな交通事故被害にあい、回復の過程で重度訪問介護の仕事に出会いました。
雪下 「大山さんが交通事故に遭われる前から、面識はありました。事故後、彼女のSNSで『土屋で働きます』と書かれているのを見かけ、コメントをしたのがきっかけで、私も土屋と関わることになりました」
当初、雪下には「障害者をサポートする」という話もあったそうですが、実際は異なる視点でサポートに関わっています。
雪下 「土屋では『サポートする側の人のQOLを上げる』という視点で動いています。障害者をケアしている側にも、精神的なサポートが必要です。少しでも心が楽に過ごせるように、アドバイスしていきたいと思っています」
障害者をケアする場合、社会の目はどうしても障害者のみに向けられがちです。雪下は、この部分に疑問を持ちます。
雪下 「サポートする側の人も、みな人間です。障害者をケアするという仕事をしながらも、さまざまな悩みや葛藤を抱えながら生きてるはず。私はサポートする側の人も、人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出してほしいと願っています。その人達のQOLを、少しでも高めるようなサポートをしていきたいです」
医師として障害者本人として、さまざまな経験を持つ雪下だからこそ、周囲が気づきにくいこと・後回しにされてしまいがちなことにも目を向けています。「サポートする側のサポートをする」という視点は、雪下ならではの視点です。
現在、株式会社土屋の顧問に就任している彼は、これからどのように「サポーターのサポート」をしていきたいと思っているのでしょうか。
雪下 「土屋のケアカレッジで、毎週サポーターに『重度障害者講習の統合課程』でサポートに関する話をしています。それを聞いて、その後の行動にも変化があれば嬉しいです」
「そういえばあのお医者さん、車椅子なんだね」といわれるような社会に

社会の需要に呼応するかのように、活動の幅を広げ続けている雪下。これからは、障害者への見方そのものを変えていきたいといいます。
雪下 「障害者でもあり医者でもあると、“車椅子の医師”と受け取られてしまいがち。どうしても“車椅子”の印象のほうが強烈なわけです。いつか、『そういえばあのお医者さん、実は車椅子なんだね』という社会になるのが、一番目指したいところですね」
雪下のこういった考えのベースになっているのは、事故後に、アメリカで暮らした経験です。
日本にいたころ、アメリカで生活している車椅子の女性の特集をテレビで見た雪下。その女性はアメリカでは不都合を感じずに生活できていましたが、帰国後日本の生活が不便で『私は日本に帰ってきて障害者になった』という内容でした。そのとき、「アメリカってどんなところなんだろう」と思ったのが、留学に行った理由のひとつだったと語ります。
雪下 「アメリカでは障害者が権利を得るまでの歴史があるので、法律がしっかりしているんです。たとえば、日本では車椅子駐車場に対象外の人が駐車をしても罰則はありませんが、アメリカでは否応なくすぐに罰金になりますし」
とにかく法律の威力が強いアメリカ。スロープやエレベーターがないお店は、営業停止になることもあります。そもそも、アメリカと日本では障害の捉え方が違うと雪下はいいます。
雪下 「障害の考え方には、医学モデルと社会モデルという2つの考え方があります。この違いは、『障害がどこにあるのか』。たとえば、『足が使えないこと』が障害なのか、『階段しかない建物』が障害なのか。アメリカでは『階段しかない建物』が障害という考え方になりますから、車椅子で生活するにあたり、障害となる部分が極めて少ないんです。当然、アメリカでの車椅子生活は非常に暮らしやすいものでした」
ただ、雪下は日本について悲観しているわけではありません。
雪下 「アメリカと日本では、社会的な構造が大きく違います。逆にいえば、日本には変わっていく余地がたくさんあるということ。いずれはアメリカのように障害者の存在が当たり前になり、みんなが暮らしやすい社会になったらと思っています」
障害が障害として存在しなくなる社会の実現を目指し、活動し続ける雪下。その経験と知識、広い視野を持って、障害に関わる全ての人達をサポートし続けていきます。