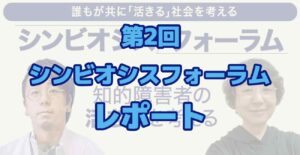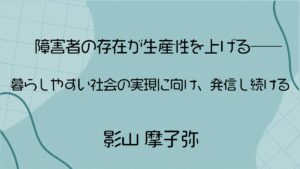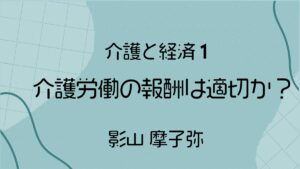一般企業での勤務を経て研究者となった田中 恵美子。「障害者の地域での生活」をテーマに精力的に調査活動を行い、大学で教えるかたわら訪問介護を行う株式会社土屋の顧問を務めています。異色の経歴を持つ田中が、障害者の生活について関心を持ったきっかけや、介護に対して抱く思いについて語ります。
研究者からソーシャルビジネス企業の顧問に。障害者の地域での生活を発信

現在、東京家政大学人文学部教育福祉学科の教員として、社会福祉士の養成などに携わる田中 恵美子。障害者の地域での生活を研究テーマとし幅広く活動する中、2020年8月に創業した株式会社土屋(以下、土屋)の顧問に就任しました。
土屋は、重度障害者に対する訪問介護サービスを全国で展開するソーシャルビジネス企業です。介護者が利用者の居宅で一対一の生活支援や医療的ケアを行い、障害を持つ人が住み慣れた地域で自分らしく暮らすためのサポートをしています。
顧問は、医師、弁護士、有識者ら6人で構成。障害者福祉やソーシャルビジネスに造詣のあるメンバーが名を連ねています。田中はその一員として、これまで取り組んできた障害者の「地域での生活」についての研究で得た経験、知見を活かした活躍が期待されています。
田中 「障害者の『自立生活』とは、重度障害者が親元を離れ、施設に入らず地域で暮らすことを指します。土屋が展開している重度訪問介護はその『自立生活』をしている人が利用するサービスになります。
私の研究は障害者の『自立生活』のほか、現在は家族を形成して暮らしている知的障害のある人たちの地域での生活も調査しています。今は新型コロナウイルスの感染拡大で難しくなっていますが、通常は訪問して、生活の様子も見せていただきながら、インタビューをさせていただくという形です」
田中の役割の一つが、これまでの出会いや体験を基にブログを作成し、情報発信すること。「知的障害のある人の結婚・子育て」「災害と障害」など、現状を肌身で知る研究者ならではの視点のブログを公表しています。近く、これらブログを含めた田中の執筆物をまとめ、土屋の出版部門から電子書籍を配信する予定です。
教育者、研究者、そして土屋の顧問と、さまざまな顔を持つ田中ですが、すべての活動に共通するのが「平等」「公平」「対等」への思いです。差別や格差を解消し、「平等」「公平」「対等」を実現するためにはどうすればいいのか──。「情報」が一つのカギになると考えています。
田中 「障害、年齢、性別、職業など、カテゴリーはいろいろありますが、これらが差別や格差にならないようにしたいと常に考えています。そのためにも『知らせていく』ということはすごく大事。今知ることができる情報を共有して、『生きづらい』と感じることを変える方法を考えていきたいです」
自分を基準に生きれば「普通」とずれて当たり前。ステレオタイプを飛び越え

現在マルチに活躍する田中ですが、これまでの経歴は異彩を放っています。
大学ではドイツ文学・時事を専攻。卒業後の1991年にはドイツに渡り、三越フランクフルト店に就職しました。ちょうどベルリンの壁が崩壊した時期で、当時の政治状況を肌で学んだといいます。約2年後に帰国、今度は手配旅行中心の小さな旅行会社に就職。ここで、障害のある人との出会いがあったのです。
田中 「旅行会社では、障害のある方たちの海外ツアーに同行しました。かなり重度の方もいて、介助要員のようなこともしました。障害のある女性の入浴をお手伝いしたところ、非常に喜んでいただけて。1週間ぐらいの旅行でしたが、すごく仲良くなれました。
すると、日本に帰る時、彼女たちは『日本には本当に帰りたくない』と言ったのです。私たちも海外に行ったら楽しいから帰りたくないと思いますが、もっともっと切実な叫びでした」
なぜ彼女たちは、あんなに日本に帰りたくないと思ったのか。日本はなぜ生きづらいのか──。旅行会社での体験をきっかけに、そんな疑問が胸に残ったという田中。そして1996年、大学の福祉系の学科に学士入学。そのまま大学院に進み、研究の道に入りました。
研究に打ち込み、人と出会い、世界が開けていくのを感じる日々。しかし、一方でときは過ぎ、当時結婚適齢期とされていた年齢を超えると、言葉は悪いですが「売れ残り」というレッテルを貼られたこともあります。
田中 「海外に行ったり、もう一度大学に行ったり、生きたいように生きると、どんどん『普通』から外れていってしまうような感覚でした。『女の人はこうだ』とか、『日本人はこうだ』とか。そういうことがいつの間にか自分にのしかかり、ステレオタイプのレールに乗らないとすごく生きにくいと。そんな中、障害のある方と出会い、似ている、同じだと思いました」
日本で女性が感じる生きにくさと、障害のある人が感じる生きにくさに共通項を見い出し、そこから「障害の社会モデル」という考え方に行きつきました。ここが、田中の研究の原点にもなっています。
田中 「今の日本社会では、障害というと『身体の特徴』ということになります。本人が努力して克服するものととらえていますが、実はそうではなくて、そういう身体の特徴を持った人を排除している社会や制度の方に問題がある。言ってしまえば社会の方に障害がある。『障害の社会モデル』という考え方はまさにそれをいっています」
数字や先入観では見えない、一人一人の人生にスポットライトを

田中が株式会社土屋の顧問に就任したきっかけは、障害者の『自立生活』のための運動を当事者として進めている安積 遊歩氏からの誘いでした。安積氏は、土屋社長の高浜 敏之と親しく、土屋の顧問にも名を連ねています。
田中 「安積さんから顧問にと言われる前に、私は1度高浜さんに会っていたのですが、起業すると聞いて最初は心配しました。今まで重度訪問介護は、当事者団体の人たちがコツコツやってきていた。ですから、株式会社として大きくやるということができるのかな、と不安があったのです。
でも、高浜さんが志高くやると言うので、できることなら応援したい。すでに大変な思いをしている当事者が経営や行政との掛け合いを自力でしなければいけないのは負担が大きいと思います。地域に暮らしている人が肩ひじを張らず、自立生活しようと思えるようにやってほしいと思いました」
田中は、重度訪問介護を事業化する難しさを感じつつ、本当に苦しんでいる人、本当に必要としている人にサービスが届いていないという現状への問題意識を抱いていたこともあり、誘いに応じました。そして、2021年10月現在、土屋は創業から1年以上が経ち、事業も順調に成長。スタッフも増えました。
田中 「増えた人たちを人数だけで捉えると、『何人』と塊みたいに理解してしまいがちです。会社として経営していくと、マスで利益とかも見ていくので当然と言えば当然なのですが、私はもう少し一人ひとりを注視したいな、と。一人ひとりが、生活の中では主人公。それぞれにストーリーがありますから、それを取り上げていきたいと考えています」
重度訪問介護に携わる人たち一人ひとりに光を当て、「重度訪問介護があるからこんな風に生活ができる」「重度訪問介護でこんな人と出会って、こんな生活ができるようになった」ということを発信していきたいと考える田中。土屋のアテンダント、クライアントをはじめ関わる一人ひとりの生活を取り上げ、共有していくことに社会変革の活路を見出しています。
田中 「重度訪問介護って、やったことがない人にはなかなかわからないと思うのです。漠然と『大変そう』というイメージがあると思いますが、もう少し違う価値を知らせていきたい。確かに大変ではありますが、それ以上におもしろいし、やりがいもある。そこの部分がまだまだ伝わっていないのではないかなと考えています。きっと伝わると信じてもいます」
生きている奥深さを肌で体感する。重度訪問介護は発見・驚き・喜びの宝庫

重度訪問介護について、大変さ以上の「おもしろさ」があると語る田中。障害のある人とともに過ごす時間の魅力とは。
田中 「障害のある人って大変だなとか、辛そうだなという思い込みがありますが、全然違う部分があるのですよ。介助も大変は大変ですが、重度の身体障害の人の場合は『こうやって』と言ってくれる。言ってもらった通りに動いてみると、必ず発見があります。こんな風なやり方なんだ、こういう風にすると結構いいかもね、とか」
障害のある人たちとは、一緒にいるからこそ経験できることが多く、それを田中は「おもしろい」と表現します。重度の身体障害がある方と接した中では、足でミシンをかける方、足で包丁を使い切ったりできる方も居られ、驚きと称賛の思いを抱いてきました。
手足が動かない方に、「冷蔵庫の2番目の奥に梅干しがある」などと、物が置いてある場所を正確に覚えている方も居られ、そんなその人ならではの編み出された生活の術が、「おもしろい」と感じています。
田中 「知的障害がある人の介助には、また別の魅力があるのです。意思疎通が難しいと思っていたのにコミュニケーションが取れたとき、言っていることがわかったと感じたときなどに喜びを感じます。これも一緒にいるから経験できる、濃密な付き合いがあるからこそわかること。
想定外のところで何かが起きるのですよね。発見だったり、驚きだったり、喜びだったり。相手のことが少しわかると次もわかるかもしれないと、介助を続けたくなるのです。一緒にチャレンジしている感覚が得られると、喜びを感じます」
重度訪問介護では、利用者と介助者との濃密な関係性がカギ。これが楽しさ、おもしろさにつながります。しかし一方で、重度訪問介護だからこその難しさがあるのも事実。田中は、土屋で重度訪問介護のリアルを伝えつつ、利用者、介助者一人ひとりの声を拾い、サービス改善につなげていきたいと考えています。
田中 「重度訪問介護では、1対1の時間がすごく長いのです。夫婦でもない、親子でもない、いわば友達以上恋人未満みたいな関係で、ずっといると息が詰まることもあるかもしれません。でも、ずっといてくれないと困る存在。介助者はそういう難しい距離感をうまくやりくりすることも必要です。
関係が一度煮詰まってしまっても、お互いがそれぞれに歩み寄ったり成長しながらどうにか乗り越えようと奮闘する、そういう輝きのある利用者、介助者、一人ひとりを本当に大切にしていかなければと思っています」
研究者として社会の課題解決に真摯に取り組む田中。今後も土屋に新しい視点や風を吹き込み、関わる一人ひとりを大切に、重度訪問介護の魅力ややりがいを伝え続けていきます。