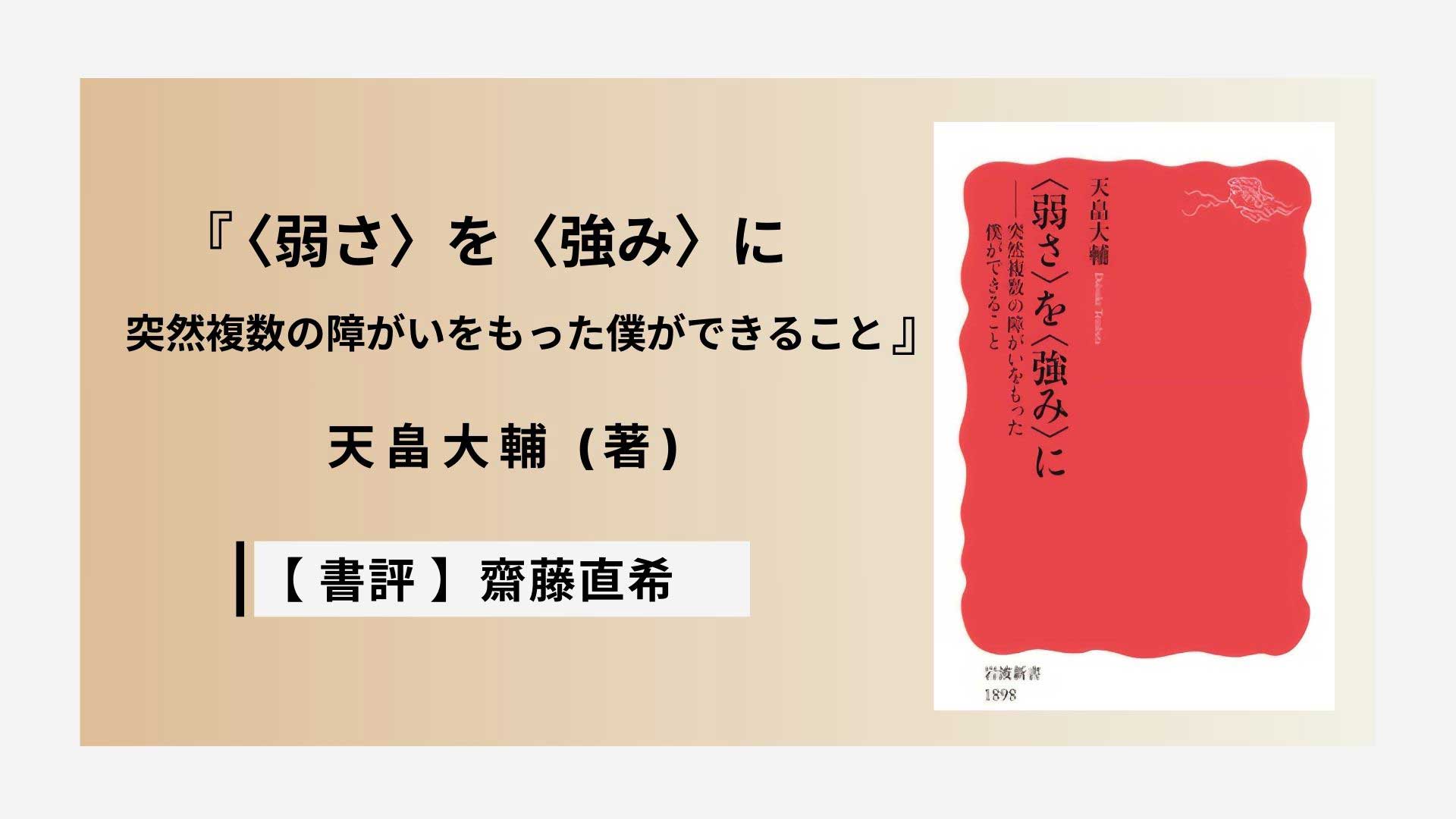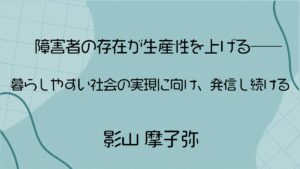『 〈弱さ〉を〈強み〉に―突然複数の障がいをもった僕ができること』天畠大輔 (著)
評者 齋藤直希
本書は、14歳まで、よく食べ、体が大きく、ガキ大将気質で、勉強もそこそこでき、進学校に通っていた“普通”の健常児(者)が、この年齢で突如、若年性急性糖尿病により心肺停止となり、
それが故に、「重度身体障がい」となって、「四肢マヒ、発話障がい、嚥下障がい、視覚障がいなど」を抱えるに至った、天畠さんという方の「当事者研究」近い書物です。
軽く読み出していると、一見、自叙伝のようにも読み取れるのですが、著者自身が、
「声に出せないあ・か・さ・た・な―世界にたった一つのコミュニケーション(出版社:生活書院 (2012/5/10))(Kindle 版. 位置NO.315)」
という自伝を出版されておられるので、評者としては文章の内容を鑑みて、障害理解を中心とする「啓蒙書」なのではないかと感じたりもしました。
著者は前述の病気に突然罹患し、低酸素脳症による昏睡状態となり、脳死状態の判定も受けたそうです(Kindle 版. 位置NO.198)。
しかしながら、入院から3週間が過ぎた頃に、著者自身は、意識が戻っているそうです。周囲の音を中心に、周囲の状況が理解できている。そのように書かれております。
ですが、その理解できている内容や状況を、周囲に伝えることはできない。
と同時に、担当医と、著者のご母堂様の、まさに「コミニケーションから隔絶されている状態」についての観察眼の違い、この大きな違いが、次のように述べられています。
【あるとき、母が僕におもしろい話をしたら、ビクッと僕の顔が動いたそうです。
母は「大輔は理解している」と感じ、脳神経科の医師にこのエピソードを伝えましたが、「考える能力はないから、違います」と冷たく返されてしまいました。(Kindle 版. 位置NO.221)】
これこそは、まさに、肉親の感覚だと思い、とりわけ医療関係者たる医師に関しては、患者と患者の家族を思いやるという意味で、評者としては、この一文のくだりは、大切なことであると、引用した次第であります。
つまりは、このようなくだりが、本書においては、随所に、ちりばめられていると、理解してくださっても過言ではありません。
評者の母親も満48歳直前1ヶ月前にして、脳梗塞及び脳出血を発症して、脳死までには至らぬものの、昏睡状態が1ヶ月弱継続しました。
入院3週間を目の前にした時に、家族が、「花壇の花に水をやらなくて良いか」と問いかけた際、「そんな水かけた方がよいべ」と一言、私の母親は急に返答し、またそのあと、眠ったり、目をあけても、視点が合わないような虚ろな状態となったことがありました。
病状などについては私の母親と著者は、全く違うものの、評者たる私たちの場合は、もし同じような状況が発生したら、看護師でもいいので、すぐ声をかけてください、という趣旨の言葉が医師からありました。
家族としては、よほどの理由でもない限り、「同じ家族にはよくなって欲しい」と考えるのが人情だと私は考えます。
ましてや、医療職たるものは、その専門性も含めて、患者家族に毅然と向かう必要な場面もあり得ると思いますが、まず一番最初に必要なことは、「よりそい」なのではないかと、考えさせられる箇所でありました。
そして、入院中のエピソードについて自叙伝的な論述がつづられていく中で、著者だけがわかる「意識の復活」、それに続くコミュニケーションが取れないことによる苦難さ=痛みを周囲に伝えられないことのとてつもない苦しみについて記述は、想像だにできないところがあります。
【生身より切り裂かれるような激痛が続き、心拍数が190を超えていたのです。しかし、その泣き叫びたくなる激痛を他者に伝える術がありませんでした。(Kindle 版. 位置NO.221)】
ICU での入院生活では同時期に入院していた子供の多くが亡くなっていく現実と、一般病棟に戻った後でも、著者自身の思いを外部に伝えることの大変さがつづられております。
自発呼吸が戻っていることが確認されても、それが故に、医師や一般病棟の看護師から、身体の大きな幼児のように扱われたとと述懐しておられます。そんな中で、たった1人、担当看護師だけが違い、
【彼は、イエスのときは右の手を、ノーのときは左手を動かす、というコミュニケーションを僕に提案して、実際に試してくれました。
(略)
彼のこのアイディアが、暗闇に閉じ込められた僕を、再び”コミュニケーションの喜び”に連れ戻してくれる確かなきっかけのひとつとなりました。(Kindle 版. 位置NO.247)】
評者は、ここにつき、著者の苦しみからの脱却、その始まりが、鮮やかに表現されていると感じました。
その後は、ご家族様、何よりもご母堂様の協力から、著者の復活が「あかさたな話法」を始点に描き出されていき、外部とのコミュニケーションについての困難性はあったとしても、一般病棟に戻る前には意識自体が戻っていること、そして
「あかさたな話法」を通じてのコミュニケーションの進化とともに、その話法を介助する「介助者との関係性の”深化”」
についても言及されており、本書の著者の日常生活及び社会生活の始まりについて詳細につづられております。
とともに、これまた本書の特徴になりますが、「コラム」と銘打って、
「あかさたな話法とは」、「特別支援学校(Kindle 版. 位置NO.617)」、「合理的配慮(Kindle 版. 位置NO.850)」、「重度訪問介護(Kindle 版. 位置NO.1340)」
など障害当事者が必ずと言って良いほど関わる「言葉」について、わかりやすい言葉で、説明されてあります。
評者が、本書をもって障害者理解についての「啓蒙書」と評する理由は、こういった点です。
著者自身の人生の歩みに加え、障害当事者において必要十分な、「言葉や用語」についての説明が懇切丁寧に記述されております。
さて著者は、14歳のとき、若年性急性糖尿病を発症し、紆余曲折を経て、安定的な健康状態に戻ったようですが、様々な障害を抱えるにいたり、重度障害者となったわけです。
四つ以上の全身にわたる重度障害を抱えるということは、中途障害という側面も含めて、とてつもない心情を察するに余りある葛藤があっただろうと、拝察しているところです。
以来著者は、入院中の院内学級に始まり、施設入所を経て、同時期に養護学校(今の特別支援校)の中学部、続いて高等部に進学されております。
評者も、義務教育は、小学、中学ともに、養護学校経験者なので、普通学校と違うカリキュラムの授業を受けていることは体験済みであります。
そしてそれが、大多数の障がい者にとって、「必要な側面もある」というところは、理解できなくもないというレベルで、私自身の中で落とし込んでおります。
理由は、普通学校には、「訓練(今で言うところのリハビリ)」という授業項目はありませんが、私が経験した養護学校には存在しておりました。
評者たる私の母親の場合、「生活=訓練。その他にも訓練のために訓練をする。身体の動かすことのできる機能を維持するため」という考え方をもっておりました。
つまり、きちんと訓練というか、リハビリをしないと、「今できること。例えばそれが、鉛筆で字を書くこと。」が、できなくなってしまう可能性があるわけです。
「今できることを維持する。できることを増やす(身体の成長や年齢も加味しながら)」というのが、私の母親の根本的な考え方でした。
そういった評者たる私(並びにその母親)の考え方と著者は、似ているところもあれば、違う部分もあると思います。拝読しながら、そのように感じている部分も、実際に存在します。
ですが、どちらが正しいとか、間違っているとか、そういう評価はありえません。ご自身の人生なので、ご自身で決めてゆく。それしかないというのが、少なくとも私の結論でありました。
ですが、著者の場合、養護学校での様々な授業については、やはり不本意なところがあったようです。それはそれで、当然だと思います。
やはり自分自身がやりたい勉強というものは必ず存在しますし、今で言うところの、「特別支援学校」というものの「本来のあるべき姿」は、個別に障害の違う子供について、それぞれの子供に必要な支援を行いながら、その子供にとっての必要な勉学を行う場所、だと思うのです。
これは評者の特別支援学校に関する個人的な私見です。しかしながら、私自身も著者も、養護学校(特別支援学校)に「物足りなさ」を持ったことは、とてつもなく理解できるところであります。
なぜならば、こと勉強に関して、評者も自分自身の体験を振り返ると、「私が望むような勉強は、結果論として、物足りなさを感じていた」からであります。
私自身の場合は、特に小学部のときは、自身の幼さもあったので、勉強についての内容は、あまり考えた事がありませんでした。
宿題が出されると淡々と行い、小学2年にして日本史に目覚め、高等部向けの図書室の日本史の本を読んでいたり、三国志ばかり読んでいたり、そのくせ、布表紙の「のらくろ(漫画、とても古いやつです。)」を読んだりしていて、一度だけですが、「小学生らしい本を読むべき」と、私と母親が担当教員に注意されておりました。
母親はそういったことに関しては、私の自由を尊重してくださいました。
ですが、様々な理由から、小学4年に股関節を手術して、あれほど訓練=リハビリをしたのに、それによって得られた、例えば「あぐらをかいて座らせていただけると、背もたれがあれば、長時間座っていられた」ということすらできなくなりました。
当時の整形手術の場合、骨が落ち着いてから訓練=リハビリを行うというやり方でした。そのためにおおよそ3ヶ月、ベッド生活でした。
そして著者と同じように院内学級というか、「ベッド学習(学級)」を行いました。その間に私の体では拘縮が起きて、筋力も衰えて、リハビリ訓練を始める前の体に戻ってしまいました。
そんな中で、親友から、「同じ高校に入ろう。(要は普通高校に一緒に入ろう。)」と、声をかけられたのがきっかけで、自分の人生を考えるようになったわけです。
その時に母親に「高校に行くのは遊びに行くのじゃない。自分の人生を考えろ!」と、叱咤されました。
他方で、手術の後も体が落ち着いても、おおよそ思春期を迎える13歳くらいまでは、失った部分を取り戻す。そのような思いで、母親の懸命のリハビリ訓練が続きました。
ある意味、「地獄の苦しみ(痛いことばかり。寒いことばかり冷たいことばかり。)」でありましたが、もともとそういった形でやってきたので、私の中では、その訓練が普通だと思ってました。
ですが、親友からの高校の誘いと、母親の叱咤がきっかけで、私自身の将来について考えるようになり、
「動けないならば、残されたのは、この頭ひとつだけ。首の上からだけ。」
と、自分の将来を考えるようになり、「勉強しなければ」と具体的に思うようになりました。
ですが、養護学校の場合、普通高校に入る受験勉強レベルの勉強は行わない。
そのようにはっきりと、告げられました。そういったところで、養護学校への物足りなさというものは、同じように感じたと評者は理解しております。
おそらく評者よりも、著者は愕然としたものと思われます。
そして本書では、著者と溝口先生との出会いや思い出、何でもできることは経験させようとしてくださる溝口先生の話が、いきいきと描かれております。
溝口先生からの「まず1年、生きてみないか(Kindle 版. 位置NO.599)」と言われた部分については、まさに、著者の「生きるスタート」を感じさせてくれます。
重度の身体障がい者は、必ずこのような出会いがないと、「通常の社会における障害者の歩む人生レール」以外の人生の選択肢を選ぶことは、不可能なくらい困難なことなのです。
それ以降の著者の在宅生活(家族生活、ご自身の自立生活、大学生活など)や、そのバイタリティーに関しては、著者ご自身が歯を食いしばって、まさに頑張ってこられたのだなと思います。
様々な「策士」のような一面も振る舞いながら、生き抜いて来られているなと思います。この生き様については、直接本書を熟読していただいた方が、間違いないと思います。
複数の重度身体障がいを抱えながら、著者本人は、その障害を感じさせないくらいな形で、人生を送られているのだなと、評者は、羨望さえ感じるところです。
そんな著者にも、評者の私も思い悩むような、事柄があるので、ひとつだけ取り上げたいと思います。
それは、著者が、博士論文の執筆について、次のように叙述されているところです。引用いたします。
【しかし、僕がこうした「おまかせ介助」の有用性を確信したのは、ごく最近です。
大学院で博論を書いていたころ、論文執筆支援の中心メンバーだった介助者Aさんから、「一文字一文字自分の言葉で書くべきだ」と要求されました。
僕は一語伝えるにも人の何百倍もの時間を要し、さらに自分の目で見て文章を確認することもできません。
なので長い時間をともに過ごし、共有知識を豊富に持つ介助者に僕の短い言葉を解釈してもらうことで、その障がいを補っています。
試行錯誤のうえ、自分に残された「考える」という能力を最大限に活かすものとして、行き着いた手法でした。
しかしAさんは、そんな僕に強く苦言を呈しました。Aさんは、僕と同性かつ同世代で、国立大学大学院の博士課程に在籍していたため、介助者でありながらライバルのような存在でした。
同じ研究職を志す者としてAさんは、介助者の意見も聞きながら協働で論文を書く僕を受け入れられなかったのではないかと思います。
言い換えると、Aさんは「介助者手足論」の考え方が基盤にあった、ということです。一文字一文字自分の力で紡いでこそ、「自分の論文」と言えるのではないか、とAさんは僕に迫りました。
僕の心は非常に揺らぎ、一時期、論文を書けなくなるほどに思い悩みました。なぜならAさんは僕にとっての「理想の研究者像」でもあったからです。
ひたむきに努力し、他者の意見に揺らぐことのない確固たる自分の主張を持ち、自分の力で論文にしていく。
僕は、そんな姿勢で自分の研究に向き合うAさんを「かっこいい」と思い、憧れを抱きました。
一方でそんなAさんに「自分一人で論文を書く」ことを求められるたびに、僕の身体の状態ではそれがいかにむずかしいことかを理解してもらえない辛さと苛立ち、「理想の研究者像」に近づけない自分の情けなさでいっぱいになりました。
いくら努力しても、コミュニケーションに介助者を介さなければならない僕は、自分の文章能力を自分一人のものとして普遍化することはできないのです。
介助者と協働で文章を作成しても「この文章を書いたのは誰か。僕なのか。介助者なのか」という問いが、再帰的に何度も何度も僕の頭を巡るのです。(Kindle 版. 位置NO.1486) 】
この引用の部分を理解する前提で、おさらいをしておくべき事項があり、簡単にまとめます。
著者の表現たる「おまかせ介助」については、引用文の前の部分で、「介助者手足論」と対をなす形で、記述されております。
「介助者手足論」というのは、文字通り、「介助者が、支援を必要とする重度障害者の『手足の役割に徹する、完全に手足となる』」という考え方であります。
他方で、著者の言うところの「おまかせ介助」というものは、著者のように、重複障害(発話障がい、視覚障がい、四肢マヒ=文字が書けない)に起因する他者とのコミュニケーションについても支援が必要な場合、
たとえばカレーライスを食べる場合に必要とされる支援で、作り方や一口の量まで意思表示するのは困難なので、
『介助者とともに時間を積み重ねていく中で、支援を受けるものと支援を行う側との間で、様々な暗黙の了解が積み重なっていき、その長い時間をかけた中で、共有されてきた介助方法に基づいて、詳細な部分を支援者たる介助者に、お任せする介助方法』
というものです。
評者たる私も、重度身体障がい者で、著者と違うところは、(現時点で)発話障がいがないこと、視覚聴覚についても、障害がなく、意思疎通について、特殊な方法によらないでいるところです。
それ以外については、日常生活で全面的な支援を要するという部分においては、一定程度の共通性は少なからずあるのだろうと拝察しております。
その上で、「介助者手足論」と「おまかせ介助」双方について、障害当事者の1人として思考した場合、「介助者手足論」、特に厳密な意味での手足論は、「机上の論理」に近いのではないかというのが、体験者としての経験知からの評者の考え方になります。
なぜならば、支援の内容を、支援者たる相手に伝えて、それを受けて、「支援者が、支援の内容についての情報を得て、手足のように動く」。
この「支援の内容についての情報を得る」時点で、多少なりとも支援者の主観が入り込まざるを得ません。
ロボットが、機械が定型的に行うことということであればいざ知らず、支援者は人間であり、その時点で、「情報を得る」「情報に基づいて、情報について解釈し、理解して動く」というところで、「手足論」は限界を迎えるはずです。
そのような延長線上で思考を続けていくと、一定程度の流れで、「(支援者たる)相手に、お任せする部分」は、必ず発生するので、そういう意味では、「おまかせ介助(論)」が、現実的であると言わざるを得ません。
評者は、一週間で、延べ人数で、40人弱、実人数でも30人超の皆様に、重度訪問介護の支援を受けながら日常生活を送っております。このような生活を始めて、最低でも8年目に突入しております。
重度訪問介護でなくて、いわゆる「居宅介護」の方も支援を含めると、制度上の支援を受けてから20年余になります。
先天性なので、患者としての経験年数は、イコール年齢、つまり半世紀以上になります。
当然のことながら、養護学校も経験し、施設生活も経験し、入院生活も経験し、普通高校と国立大学も入学・卒業しているので、著者の言わんとするところは、強く感じるところであります。
評者の評する意見に入り込みすぎたので、話を戻します。その上で、著者は、博論を作成する際に、ご自身の障害による「論文執筆支援」について、悩まれておりました。
言語表現についても、支援を必要とする著者ならではの悩みかと拝察します。
評者の感じ方としては、この引用部分こそが、本書の、「核心」だと思います。論文を書くということは、日常生活とは違うことです。
その上で時間をかければ、「著者が、一文字一文字を、言葉を紡いで論文にしていくことができる」ということを、介助者Aさんは介助者としても十分理解していると思われます。
そしてそれこそを介助者Aさんは、「著者の残存能力、極めて高度な能力」であると評価していたのではないかと拝察します。
そして、このような考え方は、どちらかというと、健常者側に出やすい考え方です。
しかし、研究者としても、介助者側としても、介助者Aさんは、「一語一句、本人作であること」の『重要さ』にも着目していたと、評者は想像しています。
また評者の経験で、恐縮ではありますが、評者は、次のような経験をしております。養護学校時代、歴史ある読書感想文の大会で、県1位となり、全国レベルに上がり、3位相当を受賞しました。
このときですが、養護学校の当時の一部の親御さんの間で、「母親(なり、誰か)が書いたのではないか」という話が、母親にも私にも耳に入りました。
読書感想文は、きっかけとしては単純に夏休みの宿題でした。そしてそれは、必要最低限の国語の先生の関わりがあった上での、全文において、原文も含めて、私の直筆による作成でした。
私としては、他者からのそのようなやっかみは、一切気にしないタイプなので、全くもって「ちくわ耳」状態でした。
それよりも、当時は、日本史の本を読むのが好きで、受賞の意味合いさえ、よくわからないくらいの勢いでした。
ですが、担当の国語の教諭いわく
「文章というものは、一人一人の個性がにじみ出てくるので、子供の書いた文章か、大人が書いた文章か、そのくらいはすぐに見破られる、だから気にする必要はない」
と母親に話していたそうです。だとすると、介助者Aさんの思いも、何となく理解できるのです。
他方で、著者は、博士論文という、極めて高度な専門論文を執筆されておりました。
評者は、学芸員の任用資格を持っているのですが、古文書についての成り立ちや解読や保存などについて、資格取得の単位の講義のときに受けております。
古文書の「書写(書き写すこと)」を行うことは、原文について、きちんと理解できる学識経験などがないと、文字自体を間違って書き写したりするので、正確性に欠けると教授されました。
「古文書の書写」の場合と、著者の博士論文執筆を同列に論ずることは、できるのかという問題はありますが、
「一文字一文字を、著者の思うところ通りに、ひとつの言葉に表し、著者の思う通りに言葉を紡いでゆく事柄」
自体に、専門性を多大に必要にされるものと評者は拝察しています。
例えば、障害者について語るときに、「合理的配慮」という言葉があります。
ひらがなにすると、「ごうりてきはいりょ」となります。これを漢字の言葉に直す時、「強利的配慮」などのように記載されては、困るわけなのです。
福祉や支援系の人ならば、或いはソーシャル系の専門家であるならば、そのような間違いを起こすことはありえません。
しかしながら、全く違う分野での関わりで、聞き慣れない言葉があった場合、その言葉の表記の仕方を間違える可能性は、大いにあり得ると拝察します。
だからこそ、研究者としても尊敬のできる介助者Aさんに、著者は、執筆支援を頼んだのだとも思います。
そのように考えると、著者が述べるように、「一語一句について、他の人と比べたとき100倍の時間をかけること。」というところの意味合いから、まさに合理性が発生すると、評者は考えるわけであります。
その上で、著者も、様々な経験をされておられることで、評者の私が経験したような「世の常」については、十二分に理解しておられると拝察しております。
だからこそ、引用文の最後のところにあったように、
【「この文章を書いたのは誰か。僕なのか。介助者なのか」という問いが、再帰的に何度も何度も僕の頭を巡るのです。(Kindle 版. 位置NO.1486) 】
という悩みに繋がっていくのだと、存じ上げます。
著者は、この悩み、「弱さ」を、「強み」に変えることによって、博士論文も含めて、人生を走っておられるわけです。
本書は、著者が重度身体障がい者になってから送った人生の荒波が、徒然ながら論理的に、まとめられています。
重度訪問介護などの制度についても、障害者の団体についても記述されております。
先天性の障がい者にとっても、重度障害者にとっても、それを支援する皆様にとっても、必ず得られるところが存在する、良書であると、評者は断言できます。とりわけ、その当事者の「ご家族」に読んでいただきたい本であります。
本書は、「親亡き後」についても記載がおよんでおります。当事者が考える「親亡き後」について記載されているものは、評者の経験上で、極めて少ないものと存じます。
重度身体障がいを背負っていても、どのように生きていくか。このように生きることができる。それについて、学びの得られる書物と存じます。
評者も、昨年親を見送りましたが、評者の人生を見返す意味でも、考えさせられる、賛同できるところ、そうでないところも含めて、考察のできる「良質な啓蒙書」でありました。
障害の種別や軽重の違いがあれど、同じ障害者として、著者のさらなるご活躍を祈りつつ、筆を置きたいと思います。
(了)
【書籍のご案内】
『 〈弱さ〉を〈強み〉に-突然複数の障がいをもった僕ができること』天畠大輔 (著)

◼︎ 評者プロフィール
齋藤直希(さいとう なおき)
行政書士有資格者、社会福祉主事任用資格者
1973年7月上山市生まれ。県立上山養護学校、県立ゆきわり養護学校を経て、肢体不自由者でありながら、県立山形中央高校に入学。
同校卒業後、山形大学人文学部に進学し、法学を専攻し、在学中に行政書士の資格を取得。
現在は、「一般社団法人 障害者・難病者自律支援研究会」代表。