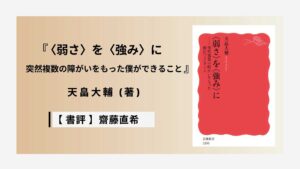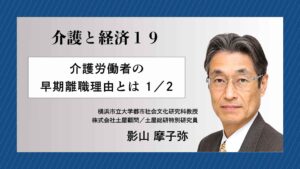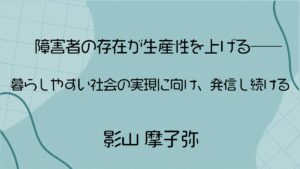『なぜ人と人は支え合うのか—「障害」から考える』渡辺一史 (著)
評者 齋藤直希
本書は、映画にもなった、「そんな夜更けにバナナかよ」(北海道新聞社、後に文春文庫)を著した渡辺一史氏による著作です。
かの有名な渡辺氏の手による書物なので、評者も、興味深く読み始めました。
本書全体に通底して文章の表現にしても、そこに根付く考え方でも、「シンプルさ」が感じられました。
また、著者も自認しているような【ノンフィクションライターという仕事柄(7ページ Kindle 版)】から来る「第三者目線」、つまり客観的な観点から書かれた文章という印象を強く受けました。
渡辺氏は、本書冒頭の「はじめに」の章で、
【人は誰しも齢をとります。そして、いつかは必ず病気をわずらって、医者にかかったり、あるいは他人のお世話になって生きていかなくてはならない時期がやってきます。
しかしこんな「自明」に思えることを、若い時や元気なときには、ついうっかり忘れてしまいます。それは驚くべき、忘れっぽさと言うしかありません。(7ページ Kindle 版)】
と書き始め「病気」そして「障害」というものが、本来は誰にとっても身近な問題であることを、さらっと述べています。
続けて「親の介護問題」という誰しも迎えるであろう課題について多少深掘りをして、「社会保障制度」「福祉」「高齢者」そして「障害者」に触れて行き、
【本書では、「障害」という問題をとおしてそれらを根底から考えていきます。
ところでみなさんが普段、障害に関して見聞きするのは、たとえば、テレビによく出てくる乙武洋匡さんやパラリンピックについての話題くらいかもしれません。私も以前はそんな感じでした。
とりわけ、重度の障害がありながらも、地域で自立した生活を送っている人たちの試みをたどることは、普段は見過ごしていた自分と他人との関わりだとか、人と社会との関わり、
あるいは、そもそも人が生きるとはどういうことなのかを考えていく上で、とても学ぶべきことが多いのです。(9ページ Kindle 版)】
と述べた上で、「初めて、目の前にする障害者との関わり向き合い」について、すなわち著者にとっては、「こんな夜更けにバナナかよ」の主人公の鹿野靖明さん(筋ジストロフィーの重度身体障害者)との出会いから、書き起し、
●生身の障害者との関わりから、「障害者」と「健常者」との境界線がいかに曖昧で、障害者の実像や実態からかけ離れていること。
●前項の「障害者」の実情や実態からかけ離れているがゆえに、社会全体で、「障害者像」というものが「建前」や「綺麗事」で満ち溢れてしまっていること。
その実例のひとつとして「障害」と「障がい」の表記問題を掲げつつ、本質的に論じなければならない「障害者に係る社会的課題や問題」などについての議論に結びつきにくくなっている社会になっていること。
●上述の鹿野さんとの関わりや、2016年の相模原市のやまゆり園事件を引き合いに出しながら、
【なぜ健常者は障害者に会うと、つい、戸惑いや緊張を感じてしまう(略)「障害者も健常者も同じ人間だ」などという理念に縛られて緊張してしまう(略)
「障害者差別だ!」などと思われたりするのも面倒ですから、そんなあれやこれやを考えると、かかわらないに越したことはない(略)(本書、14ページ)Kindle 版】
というような、一般社会に充満する障害者と健常者についての関わりの課題も踏まえて、ノンフィクションライターとして、『キレイゴトを抜きにして書いていければ』
と著者は、「はじめ」の章の段階で、簡潔に本書の目的を、明確化しています。
この最初の時点で、「障害者」と「健常者」、つまり一般的に「支えられる者と支える者」と考えられる現代社会における存在を対比して、本書の題名通り「なぜ人と人は支え合うのか」ということに思いを到らして、客観的に簡潔にまとめあげているところが、本書の「読みやすさ」に繋がっているのでしょう。
また、この問題提起ともいえる部分を、きちんと読み込み、読者自身で「考える指標」とするだけでも、本書は、十分読むに値するものであるとも思います。
その流れで、第1章の「障害者は本当にいなくなったほうがいいか」が語られ始めます。
ここでは、ALS (筋萎縮性側索硬化症)当事者の橋本みさおさんとの出会いと活動を描きつつ、橋本さんの支援の日常の風景を、ありのままに描き出されています。
続けて、障害当事者研究及び「あかさたな話法」で有名な天畠大輔さん(現参議院議員)との出会いとともに、天畠さんの重度障害に至るまでの過程とその復帰、現在の日常の支援の風景や彼の活動についても、必要十分量で書き綴られています。
そして、著者と天畠さんの共通の友人で、お2人をつなげた社会学者の深田耕一郎さん、その深田さんの人生に多大な影響を与えた新田勲さん(脳性まひによる重度障害者)との関わりについて、書かれています。
障害者自立支援運動に絡む書籍や記事に触れると、当時の障害者運動のリーダーの1人であった新田さんについては、必ずといっていいほど、そのお名前が出てきます。
当時、福祉社会学を専攻する大学院生であり、新田さんのボランティアとして自立支援運動に関わった深田さん、この2人の関係について、支援内容や活動とともに、客観的に書き進められています。
第1章は、主に先述の登場人物の人生に関わる事柄、とりわけ新田さんと深田さんの「介護を受ける・介護を行う」それぞれの立場の叙述や、障害者運動活動家としての新田さんと行政官とのやりとりの記述があります。
続いて「やまゆり園障害者殺傷事件」の概要と植松聖被告人(現在は、死刑囚)について、順を追って述べられています。
まず、言語障害がある新田さんと行政官とのやりとりは「足で書く『足文字』を使ったコミュニケーション」について次のように書かれています。
【(『足文字』がわからない行政官に対して)新田さんは、「どうだ、わかったか」という表情でこういいます。
「まず意思疎通がまったくできないでしょ。これが読めないと、介護そのものができないのです」
つまりは、こういうことです。
新田さんのように重度の障害のある人の介護には、その人になじんだ介護者の長時間にわたる見守りが絶対に必要であり、それを保障してくれなくては、障害者は生きていけない。
そのことを身をもって行政官に訴えると同時に、そこでは不思議な力関係の逆転も起こっていました。 (28-29ページ. Kindle 版)】
これは、著者も指摘しているように、まさに、「弱みを強みに」している場面です。
他方で、新田さんと深田さんとの「介護を受ける・介護を行う」という関係性における、「人対人」としての関係性について、端的に綴られています。
【「深田さんの本の中に、足文字で弱者と強者を逆転させる場面があったけど、介護者に対してはどうだったの?新田さんは、読み取りがヘタな介護者に対して怒ったり、腹立てたりとかしなかった?」
「それがなかったのが新田さんの偉いところなんですよね。介護者に対して、きみは読み方がヘタだねとか、センスないねっていうのは聞いたことないですね。逆に、新田さんがよくいっていたのは、介護ってのはお互い様なんだと」(中略)
でも、お尻を拭いてもらうときに、介護者を思いやって、少しだけお尻を上げるとか、それも新田さんにとっては精一杯の労働であり、思いやりなんだと」(29ページ. Kindle 版)】
著者は以上のように、深田さんとのインタビューのやりとりを記述した上で、
【介護とは、人間性そのものが試される場面がたくさんある仕事です。
そもそも、自分の親や自分自身のもし介護される立場になった時に、「誰にでも出来る」と思っている人に介護して欲しいと思うでしょうか。(30.31ページ. Kindle 版)】
と述べています。
「仕事」「職種」としての介護ということならば、「人間関係」という部分もさることながら、「誰でも簡単に行うことなどできず、むしろ、『個人の尊厳を大切にする現代社会にあっては、一人一人の尊厳に合わせた介護』を行わなければならないという観点から、複雑で専門的な側面を持つ職種である」と言えるでしょう。
本書の著者も、同様な考えに至ったのではないでしょうか。
その上で、やまゆり事件について、著者は、話を次のように進めて行きます。
あの事件について、『非常に気の重い話』と述べながらも、『この事件の話題に触れないわけにはいきません』と一言記してから、ノンフィクションライターらしく著者は、適切に、的確な表現で、比重も分量も、バランスの取れた形で、本書が出版された時点での事件の概要を述べています。
植松被告人の独特の考え方、つまり「障害者なんていなくなればいいと思った」という趣旨の供述及びその周辺の様々な、事件前後の植松被告人の言動に関する報道記事も正確に引用されています。
更に、本書で秀逸な部分は、和光大学名誉教授の哲学者・生物学者の最首悟さんと著者との、事件についての、本書が出版された時点でのやりとりです ( Kindle 版,pp.37~66.) 。
そこでは、哲学者・生物学者たる故の最首さんと、ノンフィクションライターの著者の専門性が、いかんなく発揮されていて、読後に圧倒されます。
この部分で、次に引用する箇所が評者にとって極めて重要な学びになりました
【近代社会そのものが、「より経済的に、より合理的に、より効率的に」を競い合い、一層の富や繁栄を手に入れようとする意味で、優生思想だといいます。
つまり優生思想とは、曲がりなりにも進歩思想を基盤としているがゆえに、根深い思想なのです。(45ページ. Kindle 版)】
この引用文の言わんとするところは、政治思想的な学問領域からの「人類や社会の進歩」を追い求めること、その進歩についてゆけない場合に、取り残される人間が発生する事によって、遺伝学的ではなく優生思想的な結果に繋がっていってしまう。
そういったことが「基盤」になりかねないという警鐘です。
とはいえ、生物的な人としても、社会的な人としても、人類は時間とともに進歩していくので、そこから取り残される存在が発生するという矛盾が産まれます。
とても根深い問題であると改めて感じます。
また、本書の中では、一つの表現として、次のように書かれています。
【自然の摂理(進化の原理)というものに目を向けると、なぜ人間社会が弱者を救おうとするのかについては、じつにさまざまな考え方や説明の仕方があります。
最もよくある説明としては、できるだけ多様な形質を持った個体を生かすことが、人間という種そのものの存続にとって有利に働くから、というものです。(54ページ. Kindle 版)】
この様な議論はよく耳にします。これに対する評者の意見を下にあえて述べさせて貰います。
この世は、諸行無常である。そして生きること自体が修行である。
これが評者の生き方の中心指標の一つになっています。誰でも人は一つの人生しか歩めません。
この世に生れ落ちてから歳を重ね、乳幼児は子供になりやがて大人になっていき、ついには病弱な高齢者になり最期を迎える。
この無情の時間の流れの中で、若くして病や障害を負ったりもする。中には評者のように、先天性の障害を抱える人間もいたりもする。
種族としての人類も永遠の存在でないかもしれません。
一人一人の人生も全て違います。これもやはり、諸行無常だと評者は思うのです。
著者は、本書の中で、次のようにも述べています。
【何千年、何万年先のことなど誰にもわかりません。
また、近い将来を考えてみても、 AI (人工知能)の発達によって、体が動くということ自体、もはや価値を失ってしまう時代が訪れないとも限りません。
現代の価値観だけで人間を判断してしまうことが、いかに危険で浅はかなことであるかがわかるでしょう。(54ページ. Kindle 版)】
これほどまでの事を、わかりやすく簡潔にまとめていること自体が、本書の価値を物語っていると思いました。
こういった、いわば総論的な話を踏まえた上で、第2章以降の各論へと話は移っていきます。
第2章は、支えることの現実を示すという上で、著者の有名な前作の出発点となる、重度身体障害者の鹿野靖明さんとの関わりについて、出会いのきっかけから、書き起こしています。
そこから、「重度障害者の地域での生活の困難さ」を示しつつ、「公的介護保障制度」の当時の未成熟さや事例について、「ボランティアによる介助、ボランティアとの関わりのリアル」について、必要十分に描き出されています。
これと同時並行で、「重度障害者にとっての自立生活とは何か」についても、著者や鹿野さんの、あるいは当時の重度障害者の考え方も含めて、分かり易く纏められています。
第3章では、第2章の展開として「福祉、介助、介護」という考え方や、その実際について話が進んでいます。
「障害とは何か」、「福祉はどのように発展していくか」、「なぜバリアフリーが進んでいるのか」、「ノーマライゼーションについての考え方」、という話に及び、「青い芝の会による社会運動」という話題を経て、「障害者の自立とは」についての考察に進んでいきます。
時代の流れに沿いながら、リアルな障害者運動と、その運動によって障害者を支える制度が徐々に進んでいく様が、対比的に述べられており、さすがノンフィクションライターの筆致であると、評者としては学び多い章でした。
第4章では、「障害とは何か」ということを考えるに必要十分な、これまでの情報を踏まえた上で、「『障害』と『障がい』の表記の違い」について、論じられています。
「障害(者)観」を前提にした上で、それの変化に伴う公的介護制度の変化についても論じつつ、『障害』と『障がい』のどちらの表記が良いかを中心に、アンケート調査の結果や、似た事例としての「痴呆症から認知症に表記が変わったこと」などを紹介しつつ、各種障害者団体のリーダーの方々の考え方が提示されています。
著者は次のように述べています。
【時代とともに、言葉や私たちの意識はどんどん変わってきます。
こうした変化は何よりも障害当事者やその家族、関係者らの切実な訴えと、それに呼応した社会の理解がもたらしたものであり、(略)時代からすると、大きな「進歩」であることは間違いありません。
それもまた、障害当事者たちが、私たちの社会を確実に動かした証といえるでしょう。(169ページ. Kindle 版)】
この「社会を確実に動かした証」が、まさに、本章における表記問題の核心部分なのでしょう。
更に第5章では、著者は、なぜ人と人は支え合うのかについて論じています。
脊椎性筋萎縮症( SMA )Ⅱ型という難病当事者の、海老原宏美さんと出会い、彼女の障害者についての考え方に引き寄せられています。
海老原さんの次のような言葉が引用されています。
【それは、障害者に『価値があるか・ないか』ということではなく、『価値がない』と思う人の方に、『価値を見い出す能力がない』だけじゃないかって私は思うんです。(174ページ. Kindle 版)】
著者は、この海老原さんの言葉の中に、第1章から提起されている「障害者はいないほうがいいのか」という問いへの真の答えを見出しているのでしょう。
そして、彼女の言葉の大元となる映画『風は生きよと言う』の公式サイトから文言を一部掲げながら「障害のある当事者にしかいえないことをシンプルかつ明快に表現しており」と評し、原文を読むことを推奨しています。
末尾で、深田さんとのインタビューに戻り、次のような深田さんの言葉が紹介されています。
【「いや新田さんはね、よく『ぼくは、人間が好きっていうことに尽きるんだよ』といってました。
それを聞いて、最初は気持ち悪ぅとか思ったんですけど、振り返ると、掛け値なしにそうだったんだろうなと思うんです。
新田さんの人生とか、書いてきたものを振り返ると、まさにそうだったんだろうなと──。
で、ぼくは、全然そんなふうには思ってもみなかったんだけど、今は、まあ、そう思ってもいいのかなと。人間っていいものだなと」(p.211). Kindle 版. 】
『この深田さんの言葉はわたしの胸に深く響くものがありました』と著者は述べています。
その上で、『人間はいいものだ』と著者に思わせてくれた鹿野さんに対する思いをつづるとともに、
【結局、私はこう考えるのです。人と人が支え合うこと。
それによって人は変わりうるのだということの不思議さに、人が生きていくことの本質もまた凝縮しているのだと。 (p.212). Kindle 版. 】
と著者は第5章を結んでいます。
著者は、「人と人が支え合う」のは人間の本質だと考え、植松被告人への明確な答えの一つを提示したかったのではないかと、評者は推察しています。
その表れとして、著者はあとがきに次のように述べています。
【「あの障害者に出会わなければ、今の私はなかった」──そう思えるような体験をこれからも発信し続けていくことが、植松被告の問いに対する一番の返答になるはずですし、植松被告に同調する人たちへの何よりの反論になるはずです。(p.217). Kindle 版. 】
少なくとも、評者もまだまだ未熟者ですが、一つだけ言えることは、
軽い重い、障害の種別関係なく、厳然として、障害者はこの世に存在し懸命に生きているということ。
そして経済で、『需要と供給』という関係性があり『供給』だけがあっても『需要』がなければ経済は成り立たない事と同じように、違う立場を語り合うことで、『自分自身という存在を初めて知ることが出来る』と尊敬する方に教えられてきましたし、私自身もそのように考えています。
結果、人間は、お互いに支え合う形が生じ、まさに『人と人が支え合う』ということが、人間の本質だと思います。
そしてそれを、作り上げてきたのが、障害者自立支援運動で、社会に訴えかけてきた障害者の先人たちのおかげだと思うわけです。
だからこそ蛇足かもしれませんが、
【制度が充実するにしたがって、今日では、そのデメリットも指摘されるようになっています。 「制度が良くなると人間同士の結びつきが弱くなる」──
海老原さんは、著書『まぁ、空気でも吸って』の中に、そんな葛藤について書いています。 (pp.201-202). Kindle 版. 】
この海老原さんの葛藤については、実際、日々大きくなっているようです。
本書は、障害者がこの世に生きる意義とともに、人と人が支え合う本質を簡潔にまとめてある良書です。
制度の骨組みができた今、海老原さんの葛藤が杞憂になるように、法制度を踏まえた上での「新たな障害者運動を模索すべき時代に入った」と評者はこれまでの思いを確信しつつ、本書の必読を皆様にお伝え申し上げます。
(了)
【書籍のご案内】
『なぜ人と人は支え合うのか—「障害」から考える』渡辺一史 (著)

◼︎ 評者プロフィール
齋藤直希(さいとう なおき)
行政書士有資格者、社会福祉主事任用資格者
1973年7月上山市生まれ。県立上山養護学校、県立ゆきわり養護学校を経て、肢体不自由者でありながら、県立山形中央高校に入学。
同校卒業後、山形大学人文学部に進学し、法学を専攻し、在学中に行政書士の資格を取得。
現在は、「一般社団法人 障害者・難病者自律支援研究会」代表。