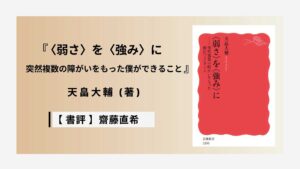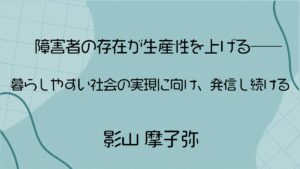【書評】『 障害者の傷、介護者の痛み / 渡邉琢(わたなべ・たく) (著) 』
評者 齋藤直希
本書の書評で、強く皆様に伝えなければならないことは、「この本は、社会福祉に関わる方は、必ず読むべき本である!それも絶対に読むべき書物である。」ということである。
本書は、著者が京都での学生時代に、障害者介助のバイトがあることを知った、というところから始まる。
それまで障害のある人との関わりはほとんどなかったと述べている著者は、いわゆる障害者や障害というものには、全くの知識も経験もない、「大多数の健常者の中の普通の一般人」だったそうだ。
そして本書は、著者が「初心者」として障害者と関わる中で体験し、相模原障害者殺傷事件に重きをおきつつ、現場の『介助者としての立ち位置』を一貫して貫いて、考察している書物である。
本書の始まりは、相模原障害者殺傷事件である。
この事件については、全く痛ましいことであるが、様々な受け取り方があり、考察の仕方があり、特にその原因にかかわるような論点については、論ずること自体が困難な場合がある。
小生のような浅学なものは、一番最初に、遺族の皆様のことを考えてしまい、論じる言葉さえ見つけるのが困難である。
だが著者は、「原因」と定義づけているわけではないが、背景として、「障害当事者と地域社会の関わり」の課題や関係性の少なさ、「社会の責任」という言葉を使い、その背景について、
「地域自立生活運動の随伴者として」という小さい題名で、介助者としての立ち位置を明確にしながら、障害者が、なぜ地域社会で生きることはできなかったのか?ということに、著者自身の職務を重ねながら洞察的に論じている。
その後に
【けれども、『障害者はいなくなればいい』という考えから自分は無縁であるとどれほどの人が言い切れるだろうか。『障害者はいなくなればいい』と思う人が多いから、地域社会から離れたところに、『入所施設』なるものができるのではないだろうか。
障害者と共にありたいと多くの人が願うならば、障害者は施設で暮らす必要はなく、地域で暮らし続けるだろう。あなたの身近には常に障害者がいるだろう。(Kindle 版. 位置 No.386)。】
と論じ、現状が違うことを指摘し、そういった社会における排除の論理的な部分が、極端な形で顕在化したのではないかと、著者は指摘している。
著者の根拠はいたってシンプルである。施設と障害者の地域生活の生活様式の違いを、著者自身の「介助者」としての仕事を通じて、そのありのままを論じつつ、重度の障害者でも、著者の所属する団体の実情を紹介しながら、障害の種別や重複障害あるいは重度障害があったとしても、地域生活が現存していることを綴っている。
その上で、現状の世の中の一般の理解は、施設でなくとも地域で暮らしていける可能性について、あるいはその事実について知られていないこと指摘している。それについての疑いを持たないことについても…。
小項目の表題として
【障害者施設で暮らすのがあたりまえか?(Kindle 版. 位置 No.419)】、【『障害者がいなくなればいいという発言に対する社会の責任(Kindle 版. 位置 No.454)】
という表現に見られるように、著者の問題意識は、あくまで「障害者(の生活の場)と地域社会や地域生活の関係性」に強く向けられている。
これは私なりの言葉に、仮に換言するならば、「障害者施設に入所するべきか否か。そんなことを考える前に、地域社会で生活できるか否か。地域社会として障害者を受け入れる努力をしてきているのか否か。
地域社会で障害者を受け入れるスタンスがあれば、おのずから、『施設入所』という考え方も、大半はなくなっているのではないか。」と言うような、著者の疑問に乗せた強いメッセージ性になって表れていると感じるのである。
その著者の疑問の向く先は、通常の概念上の「社会あるいは地域社会」ではなくて、地域社会に実際に存在する「普通の学校」や「街のレストランやお店」「アパートなどの大家さん」という、いわば地域社会の(あるいは社会の)構成者そのものに向けられている。果たして彼らは、「障害者を受け入れている」のだろうか、と言うように…。
そういった社会のあり方についての疑問を呈した上で、改めて相模原障害者殺傷事件が施設(入所者)を対象として起きてしまったかについて、丁寧に考察している。
容疑者の価値観の紹介も比較対象のために多少は掲載されているが、「障害によって意思疎通ができない」という観点よりも、
「なぜ地域社会で生活を継続できなかったのか。施設入所せざるを得なかったのか。」
という観点から、当該事件が起きたとの報道の現実を見て、「被害者、実名報道されず」との記事を見たときの著者の感じたショックについても記している。
しかしながら、事件の様態や事件の解明の段階などの理由から、被害者も、容疑者も、どちらも、実名報道が控えられる場合は、この事件以外にも存在する。
だが、著者は、前述の「ショック」つまり実名報道されなかったことについて、「障害者差別」との関連性を感じてしまっているようである。
著者は、実名報道がなかったことについて、一番最初に「障害者差別」な頭をよぎったらしい。そしてその理由を考え始めるのである。
著者は、今回実名公表できない理由は何か、それは施設が社会からタブー視されている場所だからであり、被害者の名前の公表すらはばかれるということは、入所者は、社会から忘却されるべき存在とみなされていたと言うことではないだろうか、という仮説を立てつつもそれだけでは終わっていない。
実名報道について苦悶している被害者の弟の話を引用し、障害者とその兄弟姉妹、そしてその家族、それら家族全体が、社会からの厳しいまなざしを受けていると言うことについて、「社会のあり方そのものの問題」と指摘しているのである。
と同時に、各団体の事件についての声明文について、「私たちが全力であなたを守ります。」と言うような、概ね硬質的なものが多い中で、心に沁みる記事を見つけ、
著者は、被害に遭われた方の一人一人の生活や思いに馳せることの大切さ、追悼や振り返り、そこに生きる存在の貴さや楽しみや悲しみ、喜怒哀楽に思いを馳せること、学ぶこと、考えることが大切であるという趣旨を綴っている。
それらを踏まえて、
【亡くなってから追悼していては、遅いのである。
亡くなる前になぜより多くの人とつながれなかったのか。より多くの人とのつながりがあったら、今回の事件には至らなかったかもしれない。
なぜそれ以前につながれなかったのか。それまで社会の人々は何をしていたのか。(Kindle 版. 位置 No.570)】
と発信し、ここに、本書の表題の一端である、「障害者の傷」というものが、きちんと出されているように思う。
著者はあくまでも、評者の私が触れた通り、あくまで「介助者」の視点で、もっと言えば、「現場視点」で物事について考察している。
しかしながら、「地域社会の問題課題」の一つとして障害者自立生活を考えると、例えば、
「障害児が生まれた=障害児の親になる」「障害児の親としての苦難」「障害児から障害者へ」「障害者のライフステージ」
と言うような、障害者本人だとしてもその当事者を中心に、そのライフステージを鑑みながら、血縁、地縁、社縁(利用者と支援者の関係性でも良い)といった人間社会における基本中の基本的なつながりから、あるいはそういったことを踏まえて、考察する視点をもっと多くあれは良かったかなと、評者は全体像を見て感じた。
なぜならば、「介助者」として障害者自立支援運動に著者は関わっているが、そのような目線になると、どうしても家族は「反対者」として動いてしまうからである。
だからこそ、ここまで深掘りしているので、「なぜ、家族はそのようになってしまうのか。社会との関わりは、どうなのか。(障害者の)家族と社会の関係性」について、全体的に深掘りしながら、論述していって欲しかった部分もある。
著者はかつて重度の障害者が地域社会で1人で暮らすなんて、まるで想像できなかったそうだが、たまたま実家のある名古屋に戻った際、普通のマンションの一室で24時間介助を受けながら生活している脳性麻痺の方と出会ってしまったそうだ。
そこで、重度障害者でも一人暮らしができるのだなと「できるじゃん。」と感じたそうである。
それが、学生時代に JC IL に関わり、現場にかかわるようになって、より実体感として理解するようになっていってようである。
確かに、著者の場合は、京都や名古屋を中心にその環境が社会地域として出ているので、同じ重度障害者である評者としては、「やはり西日本は進んでいるな」と感じてしまう。
【普通に傘をさして、いくらか雨に濡れながら、夜道を進む。
そして、一人暮らしをしているマンションにぼく(介助者)と帰っていく。 なにげないこと、あたりまえのことのはずだ。でも、今の社会では、いまだそうある光景ではない。街の夜の世界に、重度の重複障害者の姿は、まるでなじまない。(Kindle 版. 位置 No.789)】
とあるように、脳性麻痺の重度障害者と言え、評者の居住する街で、同様の暮らしは、さすがにまだできない。
支え手の支援者の担い手不足の問題も生ずるが、制度的に、重度訪問介護といえど、そこまでの支給量はなかなか得られるものではない。
もちろんのことながら、手動であれ電動車椅子であれ、よほど慣れていなければ、夜道を車椅子で移動すること自体が、なかなか困難な地域である。
そこはとても一般化されて、障害者全員ができると言うような感覚でいられると、相当困ると言わざるを得ない。
このようにできる障害者は、まさに「まわりの環境」に恵まれているか否か、それに尽きるものであり(評者の認識)、小生から見れば「ほんの一握り」というのが、現実論として感じるところである。
しかしながら、著者は、身体障害や知的障害など、障害種別にかかわらず、全ての障害について、「介助者」の観点を崩さずに、それでいて地域社会とのつながりを必ず添えて論述しているので、とても分りやすいものがある。
だからこそ、「必ず入所が必要なのか。地域社会とのつながりはどうだったのか」という著者の意識になるのだと考えられる。
第二章として、介助者として生きる/働くとはどういうことか、という題名でもって、まさに「介助者」という観点が前面に出てくる。
著者は、2000年頃、「障害者介助」の有償介助と出会って、自身を「介助者」と認識して、仕事がスタートした。
そうやって仕事や出会いなどを経験していく中で、「介助者」という言葉だけでなく、「介護者」「ヘルパー」「健常者」「支援者」などなどの、似て非なる言葉と出会い、それぞれの言葉の違いについても考察している。
「介助者」は、「介護」と違って「守る」と言うようなニュアンスはないとしている。どちらかと言うと、ボランティアにも近く障害者の方にとっての「手足になる」という考え方にも出会ったという。
いわゆる「介助者手足論」である。だが完全に「手足になる」というのは「そりゃ無理だ、だってやっぱり別な人」だからだそうで、クールに仕事をしていたとのことである。
他方で「介護者」は比較的、知的障害者の運動の時に使われるそうである。
介助もしくは介護に関して当事者の責任は絶対的にあるものの、「介護者」にも責任があるからということで、その知的障害者支援団体の方たちが自ら「介護者」と言葉を使っていることを新鮮だとつづっている。
「ヘルパー」については、2003年に支援費制度が始まったのが大きな変わり目だと述懐している。
支援費制度と介護保険制度が、ほぼ同時期にスタートしているところから「ヘルパー」という言葉は、日本社会全体に広がっていった。そこは評者の私も実体験しているところである。
だが、この両制度がスタートすることによって、「介助者」=「介護者」=「ヘルパー」は、「労働者」となり仕事内容として中性化していったということである。
確かに「ヘルパー」という言葉の時に、障害者運動を支える人というイメージはない。なので、障害者運動の理念を共有することの難しさも発生するとしている。
労働者としての収入も善し悪しは別として、「きちんと収入が入る」というところは大事なことであると述べている。評者も、強く賛同するところである。
だが「健常者」という言葉は、どうやら違うらしい。あくまでも「障害者運動」の場合の「障害当事者」の対極の言葉として「健常者(健全者)」として使用される場合が多いらしい。
そういった障害当事者運動は、2000年に入って、展開しにくい状況になっているとつづられている。理由は、障害者運動に若い世代がつまらない、と感じているということが大きな理由らしい。
評者も、障害者支援にかかわるものは、昔はボランティアでやっていたものが、そのほとんどのものが制度化されていると認識している。
制度化されていないものが制度化されて行き、定型化されていくとすれば、当該制度について「制度論」として手続を踏んで、新たな障害者運動を行うしかないと言う理解である。
障害支援運動に類推するものなので、それを制度化されたものが、さらに良くするようにしていくわけだから、「制度=福祉行政」について、どのような形で運用されていくのか、という決まりについて理解した上で運動していかなければならない。
つまり感情論では動かない世界となってしまったわけである。そしてこれは、評者としては障害者運動が必要ではないという考えではない。
むしろ著者のように「新しい時代に切り替わる」べき運動なのだと思う。制度理解と、制度のより良い運営について考えていくことが、障害者運動になっていくのであろうと評者は考えている。
また、「支援者」という言葉については、知的障害者の運動の中でも「ピープルファースト」という団体でよく使われる言葉だそうだ。
知的障害者を支援する運動体なので健常者だけでなく身体に障害がある方も支援者側に回るそうだ。
様々な言葉があるが、それぞれを使い分けることは、正確に使う場合、かなり困難に感じた。他方で、使い方の違いの理由として、その背景にこれほどの理由があることを、本書を通じて知った。
第三章の生存と労働をめぐる対立については、いわゆる青い芝を含めての、
1960年代からの障害者自立運動の歴史、障害者介護保障運動と高齢者介護の現状、障害者差別解消法と共生の道のり、障害者自立生活運動とそれに伴って制度化されていく過程、
と同時に高齢者についての、「介護保険制度」の確立=介護の社会化、その延長線上にある、障害者差別解消法の制定と、差別解消法が機能的に運用されていない現実が綴られている。
この章の中で、「私たち抜きにあたしたちのことを決めないで」を標語にして、
日本初の認知症当事者の会「認知症ワーキンググループ」が発足した(Kindle 版. 位置 No.3798)
という情報については、評者は本社で初めて知り、いよいよ高齢者も当事者の会を重視するようになったと、個人的に喜んでいる。
現在の介護は公的制度がメインである。すなわち制度は法制度によるものなので、主権者たる国民が能動的に動かなければ、良くはならない。
様々な意見があり、様々な国家の課題があると思われるが、それを選挙をもって主権者として行動する。
障害者自立生活運動は、ある意味、そういった側面も、意図しない部分であったとしても関係してくるということである。若者支援も国家課題としては重要である。
だからこそ、政策について、主権者として、当事者として動く意味が、高いと言えると思われる。
第四章に入ると、「まっちゃん」という著者と長年つき合いのある、それでいて著者と同世代の利用者の方の話を中心に、記述が始まっていく。
まっちゃんは、お茶目で、愛嬌があって、気さくで好奇心旺盛な方であるが、人間関係において「あるツボ」にはまると、彼の一切が豹変し、ほとんど手がつけられなくなり、誰も何ともできず、時には警察がやってきて、精神病院に強制入院させられたことが二度ほどあるそうだ。
著者は、まっちゃんの支援者であるから、「まっちゃん自身の持つ生きづらさ」について、本人自身だけが抱え込まないように、本人自身が状況を客観的に捉えられることはできるように努力するようにしている。
隠すのではなく、表に出すことで、彼の心がそういやなことにとらわれてしまわないようにするということである。そしてまっちゃん自身も、他の人に知ってもらいたいと望んでいるそうだ。
それは、地域社会から排除され忘却されるのを、まっちゃん自身が極端に怖がっているからであろうと言うことである。本人も努力しているし支援者も努力していると言うことである。
だが、現実は、日々においてトラブルは発生し、ご家族も疲弊している。彼の部屋から、暴言や怒声が続くとのことである。本人も、そうならないように努力あるいは希望しているようだが、疑問と感じる部分があるとのこと。
つまり、イライラを誘発する極限状態に強固に縛られ続け、あえてそこから離れたくない、あるいはそこに飛び込みたい、と言うような雰囲気を見せると決まるとのこと。
端からみたら、暴れている彼の方に、問題があるとしか見えないような感じとのこと。そして最終的に、「正直どうしていいかわからない」という結論に至るのだそうだ。
著者が、まっちゃんのことを、「生きづらさ」から書いた理由は、まさに彼が、精神病院入院や施設入所を強いられる恐れと毎日格闘している人だからというところから書いているとのこと。
著者は、相模原の事件から、本書を綴り始めているが、事件の背景に、入所施設という閉鎖空間での、地域社会からの隔離、排除される状況が大きく影響していると考えておられる。
その考え方を貫く限りにおいて、著者の考え方は、最後の最後に近いところまで、一貫して貫かれている。だが、現実は、困難の連続であり、施設の入所を止めることもできず、むしろ相模原に関しては、「元の形に戻して」という声があるとのこと。
施設を出たい本人と、施設こそが終の棲家と考える家族との戦い。最終的に、地域移行を進めるには、家族を強引に法的手段によって切ることでしかなかったと述懐している。
そういう意味で、介助者は傷ついてゆく。著者自身も、傷ついている。
著者は、「心的外傷と回復」という本と出合う。その本に、次のような文章があるとのこと。
【当事者は、無名性にとらわれている状態から解放され、自分の体験に当てはまる言葉があることに気づく。自分がもはや独りではないことに気づく。同じように苦しんだ人たちがいるのだ。
さらに、自分がクレイジーでないこと、外傷性症候群は極限的な情況における人間の正常な反応なのであるということを知る。(Kindle 版. 位置 No.4797)】
著者は、支援について、依存性があったり様々な困難性な部分があったりといった感覚は、当事者と支援者の間で、同じような感情になってしまったりが、エスカレートするような形で伝播していくと述べている。
そして信頼関係が破壊され、再構築されることを繰り返すとのこと。
そしてそれは、当事者と介助者との関係性であれば、あるいはそうでなくても(人間関係性において)誰しもが、置かれている状況によって起こりうるものであると(戦争など)いう。それが、殺意にも繋がって可能性がある、と。
おそらくは、極度な極限状態によって、無感覚のうちに、通常では気づかないような形で、進んでいるように理解されているようである。その核心にあるのが、「独り」ということらしい。
評者には、到底想像だにできない極限状態なのだろうと思われる。だが、評者も重度の障害を抱えているか、それに似ている感情に、さいなまれたことはないかと振り返ってみた。
殺意などにまでには感じはしないが、孤独というものは、私にとってもとても不安なものである。
支援する、される、そういった観点から考えても孤独は不安であり、障害者虐待の中でも「ネグレクト(無視)」が、何気に一番と怖いものであると評者は考えている。
この考え方は、本書で著者が指摘している部分と近いのではないかと、感じざるを得ない。
そして著者は、その行きつく先を、「言葉を失うとき」と捉えているようである。これは単純に、「意思疎通ができない(手段としてできる、できないという意味ではない)というものと違う」と理解している。
人間同士としてのつながりが、完全に持てなくなる状態としての「言葉を失うとき」というように考えているようである。
なので、つながりを持てる形であれば、「表情を取り合うことでの『言葉』」のやりとりでも、つながりを持てるという考え方である。
著者は、最後にこのように書いている。
【言葉を失った人たちの言葉は時宜に応じて取り戻されることもあるし、取り戻されないこともある。
いずれにせよ、彼らとのつながりを断ってはならないし、彼らの思いや記憶は、例え彼らの口から語られることがなくとも、私たちが、絶えずそこに思いを馳せ、その残響に耳を傾け、さらにそこに応答していかなければならないことではないだろうか。(Kindle 版. 位置 No.5769)】
著者の介助者としての姿勢については、私には想像だにできない。だが評者も支援を受け続けて20年、家族支援も含めると、生まれてからずっとである。
家族支援の方が本音は出やすく、その中で、戦いのような毎日を送ったときもある。支援を受ける側も大なり小なり傷ついているのだ。
本書は、本当に現場目線での、障害の種別、軽い重いを越えて、支援の現場について、深い考察を加えてある良書である。
福祉にかかわる人もちろんのこと、どんな人が読んでも、必ず学びにつながる良書であるということだけは、強く伝えたい。
(了)
【 書籍のご案内 】
http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3235

◼︎ 評者プロフィール
齋藤直希(さいとう なおき)
行政書士有資格者、社会福祉主事任用資格者
1973年7月上山市生まれ。県立上山養護学校、県立ゆきわり養護学校を経て、肢体不自由者でありながら、県立山形中央高校に入学。
同校卒業後、山形大学人文学部に進学し、法学を専攻し、在学中に行政書士の資格を取得。
現在は、「一般社団法人 障害者・難病者自律支援研究会」代表。