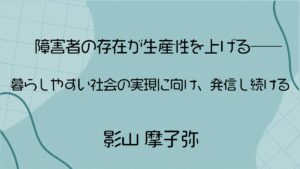【書評】『 障害者差別を問いなおす / 荒井裕樹 (著) 』
評者 齋藤直希
本書は最初に、障害者差別を扱うに当たっての、「差別」という言葉自体についての国語的な説明や「障害者差別解消法」についての説明がある。
そして、障害者差別解消法についての著者としての説明や考え方が叙述されていく中で、【 誰かが殺されても気にならない社会 】の節に【 私たち市民一人一人も、この惨事を真摯に受け止めようとする意志が不十分であるように思えてなりません(これは多分に自戒を込めて申し上げます)。(Kindle 版. 位置No.140) 】
という件がある。
とかくネット社会になり、ネット機器を通じて、一人一人が、社会における溢れんばかりの情報に容易にアクセスできるような世界になったと同時に、容易に1人の人間が情報などを社会に、世界に発信しやすい状況になっている。
他方で、「情報の消費」がより加速度的に進んでいるように感じられ、日々を生じる社会的な問題或いは社会的な事件について、風化する速度は極度に早まっているように感じる。
確かに、2010年代後半から、いわいるマイノリティーと総称される人たちへの不寛容な価値観や事例や差別的な事柄は、目まぐるしく発生していて、「多様性のある社会」が標榜する中で、それらが、まさに日常生活空間の中で、状態を変え、形を変え、発生してくる。そして社会が混沌としている。
著者は、このような社会にあって、
【 こうした混沌とした時代状況の中で、私たちは「障害者差別とは何か」という問題について、一から考えなければなりません。
とは言っても、そもそも「障害者差別とは何かについて一から考える」とは、具体的にどういうことで、どのような作業が必要になるのでしょうか。
様々な議論の仕方があり、多くの視点から検討されることが必要だと思いますが、私は「障害者差別が問われた原点のことを調べ直し、現代に通じる問題を見つける」という方法をとりたいと思います。(Kindle 版. 位置No.191) 】
というように述べている。
そこから始まるのが、【 第1章 「差別」と戦い始めた人々 】ということになる。
内容的には、脳性麻痺重度障害者に対する差別、その差別と向き合う団体としての「青い芝の会」の障害者運動の話であり、障害者差別の生の声や、団体の運動の歴史が、丁寧に一つ一つ、個人名も掲げながら、著述されていく。
もちろんのことながら、「脳性麻痺」の障害の詳細もきちんと述べている。
始まりは1950年代前後くらいからの話である。
そして障害を持って生きていくこと、すなわち生命維持自体の困難さ、それを踏まえての当時の考え方としての最前線となる「コロニー構想」にも触れている。
介護制度もない時代であり、それ以前に障害者が教育すら受けることのできない時代、つまり重度の障害がゆえに「義務教育免除」が当然のごとく適用されていた時代。
当時は、家族介護だけが、障害児者にとって、生きるための術だった。
この章で著者は、『しののめ』という文芸誌を掲げながら、二つの詩を引用している。
【母よ 不具の息子を背負い、
幅の狭い急な階段を
あえぎながら這い上がる母よ
俺を憎め(以下割愛)
私の朝は母を呼ぶことで明け
私の夜は母を呼ぶことで更けてゆく(以下割愛)
(Kindle 版. 位置No.310)】
評者が、この詩の一部を引用したことには理由があり、とりもなおさず、評者たる私自身も、脳性麻痺の重度身体障害者であり、実体験として、母におんぶされ、母に頼って、しかも夜中の排泄があったとしても、母に頼ってきたわけである。
このように、様々な文献を掲げつつ、「青い芝の会」、「川崎バス事件」、「障害児殺害事件」について、1950年代、そして60年代以降も含めて、丁寧に書き綴られている。
【 第二章 障害者のままで生きる 】については、青い芝の会の「源泉」ともいえるマハラバ村における脳性麻痺当事者の共同生活と、大仏空(僧侶、社会活動家)の思想的な部分についても述べられていて、
【 障害者は「健全者」に気に入られようと思ってはいけない。障害者がすべきことは、「健全者」に認められようとして「健全者」に近づく努力をするのではなく、「健全者が作った社会の価値観それ自体を問い返し、背を向けていくことである。(Kindle 版. 位置No.492) 】
といった考え方が、後の「青い芝の会」の行動綱領に影響していると、著者は記述している。
そのあと、【 第3章 「健全者」とは誰か 】に続いて、【 第7章 障害者は生まれるべきではないのか 】まで、『しののめ』『マハラバ村』『青い芝の会』を中心に、それらに関わった障害当事者の様々な言葉を拾い上げ、時代背景もかんがみながら、叙述している。
障害当事者の、差別以前の「無理解の時代」からの記録集的に、本書をみていくと、その丁寧さと正確さも相まって、非常に良書といえる。
他方で、あとがきにおいて、著者は、
【 「障害者差別」をテーマに掲げた書籍としては、本書は、少し風変わりな一冊になったと思います。
扱った事例は身体障害(特に脳性麻痺)だけであり、また「障害者差別をやめさせるための有効な手だて」や「障害者差別解消法に違反しないための適切な対応例」といったものも提示していないからです。
タイトルだけを見て本書を手に取った読者の中には、こうした内容に不満を抱いた人がいるかもしれません。 】
と記述しており、著作者自身が、偏りがあることを認めている。
続けて、
【 確かに、差別は人の生命と生活を脅かし.心と尊厳を傷つけます。決して許してはならず、即効性のある対策を取るべき場面も多々あります。
しかし、また一方で、差別は往々にして入り組んだ背景を持ち、明確な解決策を示しにくい場合があることも事実です。
直面している問題が大きければ大きいほど、また複雑であればあるほど、特効薬や対応マニュアルを求めたくなるのは自然な人情かもしれません。
しかし、余りにも早急に(あるいは短絡的に)「解決」を求める発想には、どこかに危険が伴うことを指摘し続けることも必要だと思っています。(略)
では、本書の著者である私にできることは何か。それは「過去、この社会の中で、障害者本人たちが、特定の言動や価値感を『差別』だと受け止め始めた経緯について、具体的な事例を一つ一つ調べていく」という作業です。 】
と述べている。
確かに、著者の言っていることは、極めて妥当だと思われる。
だが、果たしてそうであろうか。
第二章あたりまでの本文の中で、本書がいかに障害当事者の文献や発言録などについて詳細に丁寧に拾っているかについては、評者なりに、掲げたつもりである。
ただ、何ヶ所かで違和感もあった。
一つ目として、【 第6章「障害者にとって『普通の生活』とは何か 】で、通常呼ばれるところの「バニラ・エア問題」について、著者は取り上げている。
そしてその検証の比較対象として、青い芝の会が行った「川崎バス闘争」を挙げ、「差別」について検証ないし考察をしている。「差別」についての書籍なので、検証や考察を行うことについて異論はない。
しかしながら、「時代が違えど」、同じ「公共交通手段についての差別」というところだけで、「バニラ・エア問題」と「川崎バス闘争」を、「差別の検証」として、比較考慮してよいのだろうか。
確かに、障害者差別解消法が制定されて、くしくも今年の4月からは民間事業所も、合理的配慮は義務化された。
それでも、「義務化」されたのは、「合理的配慮」を行うことである。
と同時に、あとがきの中でも、「余りにも早急に(あるいは短絡的に)「解決」を求める発想には、どこかに危険が伴うことを指摘し続けることも必要だと思っています。」と著者は述べ、「川崎パス闘争」を引き合いに出しながら、
【 まず、介護人というのは特定な人がやるものであるという発想自体まちがいであり、この社会を構成する健全者すべてが介護人であると我々は考えているし、そうした考えにたてば、街ゆく人も、バスの乗客も、障害者本人が介護を依頼し、それに手をかした人はすべて介護人であるはずです。
(『母よ!殺すな』三〇一頁)
( Kindle 版. 位置No.1638) 】
と横塚晃一氏の発言を引用している。
その上で、
【 こうした問題が繰り返し起きているという点を鑑みれば、私たちは、まだまだ横塚晃一が視聴したような(発想の転換)までには至っていないようです。( Kindle 版. 位置No.1672) 】
と論じている。
評者自身も脳性麻痺の重度身体障害者である。
ゆえに、横塚氏のいうような「介護人」のあり方は、ベストな理想かもしれない。
だが果たして、そのような理想はあり得るのだろうか。
評者は、「非現実的である」と断じざるを得ない。
そもそも、「様々な問題事を解決すること」のためには、背景も含めて、「段階を踏んで、総合考慮の上で解決を図っていく」ということが肝要であると評者は考えている。
「交渉を行う」という手段でも、同じテーブルにつかなければ、話し合いにはならない。
法的手段を選択したとしても「手続法分野(例えば民事訴訟法など)」が存在する。
「階段を踏みしめるように」少しずつ手続を踏んで階段を一段一段上がっていくように、解決の糸口を探りながら、行っていかない場合、「社会からの理解」は、得られないであろう。
「バニラ・エア問題」については、本来であるならば、様々な角度から、「差別」と「合理的配慮」について、検証していく必要があると考える。
そもそも論で「バニラ・エア」という航空会社は格安航空 LCCであり、奄美空港、つまり空港側の設備状況に影響されている部分が少なくない。
だが、現時点で、評者が在住する県のメインのバス会社では、
『※車椅子非対応の車両で運行する場合がございますので、ご利用の際はあらかじめ運行営業所にお問い合わせください。』
と明記されている。
と同時に、障害者と一言に言っても、一人一人、障害の実態は大きく異なっている。
例えば私の場合で言えば、バス停で待っていること自体が、「合理的配慮に欠ける」と言えるような状態である。
つまり重度ということである。
昨今叫ばれている「人口減少化」が進めば、公共インフラは劣化し、その維持自体が大変になってくる。
そのような時代背景の中で、「非現実的な」主張は、通じるであろうか。
「差別」も「優生思想」も、両方とも、考え方としては、許し難い考え方であり、とりわけ「優生思想」自体については、「絶対的に許すべき考え方ではない」と考える。
だが現実的には、賛否両論のある現代社会の課題として、「出生前検査」などもある。
複雑化している現代社会において、単純に、「差別」論だけで、論じることができなくなっていることは、明白になりつつある。
著者は、「障害者の生きる意味の立証責任」の困難さについても論じている。
評者として、この点について考察してみたいが、その前に私自身の障害者としての経験について、多少触れておく。
私自身もまず、脳性麻痺の重度障害者である。
その上で両親について述べると、父親には、世間体に隠すという前提での、家庭内における虐待癖があった。
私は幼少期から、毎日中指の広い爪で叩かれ、「何でお前のようなゴミ人間が生まれてきたんだ。この人間のなり損ないが。早くくたばってしまえ。お前を殺すのなんか、首をちょっと抑えれば、あっという間だ。そもそも、何もしなくても、それだけでお前は死ね。なにもない所の外国などに生まれ落ちたならば、一日も生きられないだろう。」
と、様々な形での虐待を経験している。だがそれ以上に私として辛かったのは、母親も責められていたことである。「なぜこのようなゴミ人間を産んだ。」などなど。
そんな中で私は生まれ育ち、母親から毎日のように訓練を受け、「お父さんに負けない。いろんなことをいう社会の人に負けない。だけれども、できることは自分で頑張り、できないことは、何度も、何10回も、お願いして、お願いして、お願いされる人の気持ちになって、物事を人に頼るようにしなさい。」
という趣旨のことを、厳しい毎日のしつけの中で言われてきた。
振り返るに、私自身がちょっと変わっていて、小学2年時で、大河ドラマで日本の歴史に目覚め、それ以降、漫画の日本史から始まり、それで、漢字を全て覚えるくらいだった。
小学4年時の時には、「摂政、関白、太政大臣、征夷大将軍」有名どころだが、平気に漢字書いていて、自分で満足している、変わっている子供時代であった。
もちろん他の漢字も、養護学校の図書室の歴史の本で、覚えてしまっていることは言うまでもない。
と同時に、このように自由に、書物と関わるというか。
自由に勉強をできる環境は、母親からの「守り(父親からの)」のおかげであった。
時代背景も、状況も違うので、本書に出てくる数多くの重度障害者よりも苦労しているとは言えないし、述べるべきでもない。ただ私が言いたいのは、私自身が脳性麻痺の重度身体障害者として、幼児期から、様々な困難と痛みと苦しみと忍耐と、一言で言えないほどの大変さを経験したことがあるというそのことだけである。
他方で、父親と違い、母親の場合は、「家の中にいつまでも隠すことはできないのだから、外に出さなければ。。。」という考え方で、いつも父親とぶつかったり、父親の機嫌をとったり、様々な手を尽くして、兄弟も含めて、苦労しながら、母親なりに兄弟ともに公平に育てるように努力していた。
父親は、 DV (家庭内暴力)の教科書のごとく「緊張の蓄積期」⇒「暴力の爆発期」⇒「解放期(安定期)」と、典型的なサイクル通りの言動をとっていた。と同時に、世間にはとてつもないほどに気を使い、家庭内で家族の皆が苦しんでいることは、表に出さないようにしていた。
しかしながら、虐待癖のある父親も、昨年他界した。
どのような存在であれ、「人一人が、死ぬということ」は、極めて周囲に多大なる影響を及ぼす。
父親が亡くなったとき、言葉にできない虚無感に私はさいなまれた。
親戚や、周囲の人も、悲しんでくれた。
「人の死というものは、大切なものであり、変え難い価値のあるもの」と言えるのではないかと、私は気づいた。
いわば、「武士道の死生観」のようなものであり、「尊厳死」の時に語られる言葉のいくつかが、脳裏に浮かんだ。
「死」ということ自体が、尊く大切なものであり、そこから導き出される「生きることの大切さ、尊さ」これこそが、障害の有無にかかわらず、「生きる意味」の証明とはならないだろうか。
つまり、尊い「死」だからこそ、何人も侵すことが許されないのではなかろうか。
確かに、身体障害と知的障害の両方について重複している重度障害児者についても、養護学校なども含めて、関わったことがある。
重度の障害がゆえに、本人だけの力では、「生」「死」について、複雑に考えることは困難な方が存在されていることは十分、私も存じ上げている。
だからといって、その方の周囲の部分には、家族や親戚がいて、そこに様々な人間関係が、社会関係が存在しているはずである。
それだけで、十分尊いといえるのではなかろうか。
そしてそれ自体で、十分、証明できていると、言えるはずである。
私は、私自身のことをして、「私自身は、動けない老人に早くなりすぎた。」と、考えたり表現したりする時がある。
人間=ホモサピエンス、という生物種は、必ず老いて心身ともに衰えて、様々な人に助けていただきながら、命の終わりを迎える生物種なのである。
それ以上でも、それ以下でもないのである。
だからこそ、改めて当然のことながら、「優生思想」なども、もってのほか、の事柄なのである。
「差別」の話に戻る。
「差別」を受けるのは、障害当事者だけなのであろうか。
その家族などは介護などで大変というだけなのだろうか。違う。
少なくとも、私の周囲では、そうとは言えなかった。生前、父親は、落ち着いている時、「職場の周りの、同僚もな。障害のことなんか、全然わかろうともしないし、わかる気もないし。
俺(=父親)だって、男としてのメンツ、面目もあるし。悔しくてな。」と何度も言っていた。
時代背景もあって、当時の社会背景において、私という「障害児の父親」という差別を、仕事を続けなければならないというところにおいて、差別について忍耐をしなければならなかった。
この世の中には、様々な「差別」がある。
「差別する者」そして、「差別されるもの」。
それぞれの心の中に、「差別感情を抱いたとき」、その時から、「差別」というものは生じてくるものと私は考えている。
そして「差別」の出発点は、「差別感情の発生」の前提として、まず「区別」というものが行われている。それも、例えば、「高齢者と成年」「子供と大人」のような、単純な違いを表すだけの区別のためだけの表現ではない。
その存在場所も含めて、区別され始めるときに、それぞれの存在についての理解が失せていって、例えばそれぞれの存在についての不安な気持ちなども相まって、発生してくるのではないだろうか。
だからこそ、特に現代社会においては、「地域共生社会実現」という言葉で表すようになってきているように、障害者が地域で常に、目に見えるところに存在し、社会活動や生活ができるようになっていかなければならないと考えている。
区分けされ、分断され、リアルな目の前のところに存在しない段階で、「差別の端緒」になりかねない。
極めて広義な観点では「性差別」に関連するような言葉は増えてきた。
しかしながら、「ハラスメント」という言葉は、「嫌がらせ」として原則使う言葉であるので、重なる部分は生じるとしても、「差別」とは根本的には違う概念である。
「差別」というものは、「不当な取り扱い」をされることだったり、「該当者に対して不当に蔑む感情」を表す言葉だと理解している。
だが「ハラスメント」については、先程述べたように「嫌がらせ」というものが本質である。
「バイオレンス」に至っては、「暴力」なので、より直截的に「刑罰」に近い概念である。
もちろん「差別」とて、状況や事案によっては、「刑罰」に近づくときがあるかもしれない。
だがむしろそれは、現代の言葉で言えば、「虐待」ということになってゆく。
そしてそれが関連する言葉ということであるならば、「障害者虐待」という言葉で、障害者の方も「言葉のバリエーション」は、増えていると理解しなければならない。
「セクシャル・ハラスメント」をはじめとする「ハラスメント」は、どちらかというと、「性差別」の延長線上として言葉のバリエーションが増えていたということよりも、「ハラスメント=嫌がらせ」という方向性で、言葉のバリエーションが増えている。
例えば「モラル・ハラスメント(モラハラ)」や「パワー・ハラスメント(パワハラ)」などである。
少なくとも、モラハラとパワハラは、「性差別」に立脚した概念ではないであろう。
もちろん対人関係の問題であるので、「性差」という部分でかかわらないとまでは言わない。
だが本質ではないであろう。
他方で、「感動ポルノ」については、ほぼほぼ、「障害者」や「難病者」について、特化して使われる場合が、ほとんどである。
そういう意味では、「障害者(差別)」の方が、言葉のバリエーションが増えた、とさえ言えてしまう。
本書は、「差別」の中でも、「障害者差別」、その中でも「脳性麻痺の重度障害者」の当事者の、社会で生き抜く困難さや運動の歴史などの事実、「そういった具体的な事例を一つ一つ調べていく作業」の集大成となっている。
その本書の題名が、「障害者差別を問いなおす」と銘打っている。
つまりは、本書を通じて、「(読者の自らの頭で)我がことのように、障害者差別を問いなおす」を主目的に、置いてある本なのではないだろうか。
「差別」は、人類の歴史を振り返るときに、それを完全に解消することは、かなりの困難な事柄であると認識している。
だからこそ、「差別」解消について、「諦めるのではなく、継続にして、不断の努力を行う」ことこそが、大変重要であると、改めて強く感じる。
そして今、長い障害者差別の歴史の中で、法的にも整備されつつ、社会生活の支援も大きな枠組みとして作り上げられつつある。
これからは、それらの円滑な運用を求めていかなければならない。
ここまでこられたのは、多くの困難や苦しみを乗り越えて障害者運動や大変な生活を乗り越えてきた、重度障害者をはじめとする、障害者問題に関わる多くの先人の努力の結晶だと考えている。
本書は、その偉大な先人たちの事例を丁寧に取り上げ、まとめ上げ、必要に応じて、原点に当たってみたり、「障害者差別」あるいは「差別そのもの」について、考えるきっかけを読者に与えている。
とりわけ、「障害者支援」に関わる方については、本書を一読されることを強くおすすめする。
障害者と、その障害者家族、社会がどのように動いてきたか。
どのような大変さと困難さがあったか、その思いはどうだったのか。
自分の頭で考えながら読み進めることができる良書である。
【 書籍のご案内 】
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480073013/

◼︎ 評者プロフィール
齋藤直希(さいとう なおき)
行政書士有資格者、社会福祉主事任用資格者
1973年7月上山市生まれ。県立上山養護学校、県立ゆきわり養護学校を経て、肢体不自由者でありながら、県立山形中央高校に入学。
同校卒業後、山形大学人文学部に進学し、法学を専攻し、在学中に行政書士の資格を取得。
現在は、「一般社団法人 障害者・難病者自律支援研究会」代表。