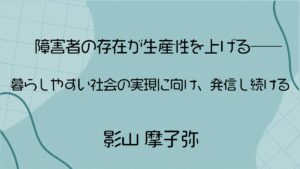労働生産性と働き方
株式会社土屋顧問/土屋総研特別研究員
影山 摩子弥
【労働生産性の意味】
経営学は、経営に関する学問です。つまり、企業をどのように運営していったらよいかを扱う研究領域で、経営者にとって重要な領域です。
そのため、経営学では、人をどのように扱えば生産性が高まるか、よく働くか、どのような組織だとイノベーションが起こるか、様々なリスクを回避できるか、どうすれば顧客に評価されるかなどが扱われてきました。
その中で、常に関心が寄せられてきたのは、労働生産性です。労働生産性とは、どれほどの労働量でどれほどの付加価値が生み出されたかを示すものです。
付加価値とは、企業が新たに生み出した価値のことです。企業は、原材料や機械を買い、従業員を雇って製品を作り、その製品を一定の値段で売ります。原材料はその企業が作ったものではないので、「新たに生み出した価値」ではありません。新たに生み出した価値は、「売った価格-作るのにかかった費用」です。これを付加価値と言います。正確には、控除法もしくは積上法という方式で計算されます。前者は中企庁方式、後者は日銀方式とも言われます。
<控除法の場合> 付加価値 = 総生産高 - 外部購入価額(直接・間接材料費+買入部品費+外注加工費+運賃など)
<積上法の場合> 付加価値 = 経常利益+人件費+金融費用+減価償却費+賃借料+租税公課
ですので、付加価値は、金額で表記される厳密な数字であり、有用性が高そうといったイメージを意味するわけではありません。ちなみに、一国の付加価値を総計したものが、いわゆるGDP(Gross Domestic Product=国内総生産)です。
付加価値は必ずしも利潤とイコールではありませんが、利益につながります。そこで、労働生産性を上げることが経営課題となり、経営学の重要なテーマともなるのです。
【労働生産性を上げるには?】
労働生産性は、付加価値÷労働量 です。
労働量を従業員数にすれば、一人当たりの労働生産性となり、従業員数×一人当たりの労働時間とすれば、従業員1人1時間当たりの労働生産性となります。
なお、付加価値のところをGDPとし、労働量のところを就業者数とすれば、就業者一人当たりがどれほどのGDPを生み出しているかを示すことになります。これを、国民経済生産性と呼びます。
計算式上、労働生産性を上げる要素は2つです。①付加価値を増やす、②労働量を減らす、です。
付加価値を増やす場合について考えてみましょう。積上法の場合、付加価値は、経常利益+人件費+金融費用+減価償却費+賃借料+租税公課ですから、人件費が上がれば付加価値が増えることになりますが、販売価格が同じで金融費用以下も同じであれば、経常利益が減ります。経営側としては面白くありません。よく行われるのは、人件費を下げて経常利益を増やす方法です。ひどいですね。生活は楽にならないのでいっぱい働かねばなりませんし、子どもがそのような生活を送らないよう教育費をかける必要も生じ、少子化が進展します。その結果、深刻な人手不足となっています。さらに、社員のモチベーションを上げる課題が常に生じています。企業は自分で自分の首を絞めているのです。
なお、「良い仕事をする」ことも付加価値を増やします。良い仕事をすれば、今までよりも良いもの、つまり高く売れる生産物やサービスを生み出すことになるので、付加価値が上がるということになるわけです。
他方、労働量を減らす方も問題をはらみます。技術革新等で、今までの従業員数や労働時間よりも少ない時間で相対的に多く生み出すのであれば、労働生産性は上がります。しかし、それほどの技術革新ができるとは限りません。
そこで、同じ人数でいっぱい働かせ、いっぱい生産させます。成果主義を背景にパワハラで(つまり、脅しの成果主義で)今までよりもたくさん生産させたり販売させたりすれば、生産量は増えます。その際に、サービス残業をさせれば、人件費部分はあまり増えないので、利益が増えます。
これでは働く側はやってられません。モチベーションが落ちますし、いい会社だと思えませんから、かえって労働生産性を落とします。